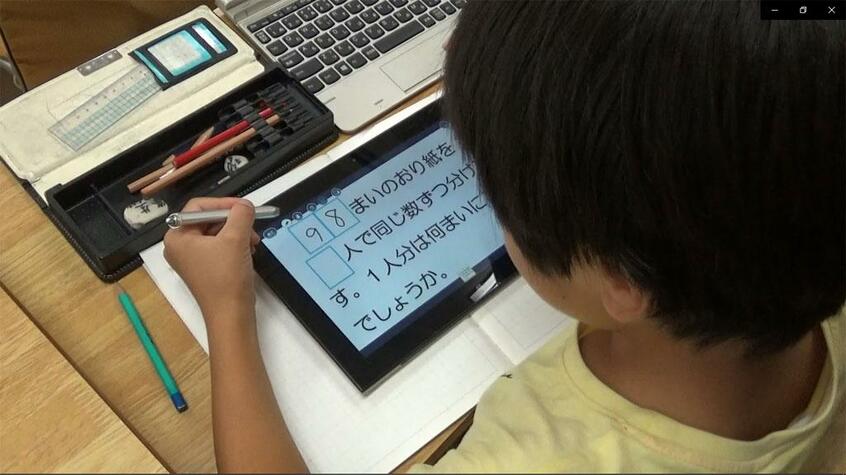

東京・杉並区では2019年度から、「個別」「探究」「協同」の3つをキーワードに「学びの構造転換」を始めた。これまでの何を変えて、どのような成果が得られたのか。AERA 2021年6月21日号が取材した。
* * *
「なぜ子どもたちへの問いを『生き方』に限定し、私たちが期待する正解が透けて見える展開にする必要があるのか?」
東京都杉並区の、ある小学校。6年生が学ぶ国語の進め方についての議論だ。
題材は立松和平の小説『海の命』。主人公が村一番の潜り漁師だった父の命をクエに奪われ、父が死んだ瀬で毎日一本釣りをする人物に無理やり弟子入りするところから、話は始まる。
■多様な解釈を認める
教科書例題は「登場人物の関係を捉え、人物の生き方について話し合おう」。本来ならそれに沿い、6時間程度で単元を構成する。しかし、教員たちは「子どもたちのより深い学び」のため独自のアプローチを探る。
「私たちが文学に触れる接点は、必ずしも『生き方』だけではない」「では『いちばん感動したところ』を中心に読ませてはどうか」「いや、なぜ『感動』でなければならないのか」
教員たちがたどり着いたのは「子どもたちが自分で問いや課題を立てる」ことだ。「生き方」に限定しない。叙述に基づくなら「つまらない」という感想があってもいい。「私はこう読んだ」という、多様な解釈を持ち寄る授業にしようと考えたのだ。
「自分で問いや課題を立てると、一人ひとりに固有のエピソードや生活体験が現れてくる。それが相互の触発を促して学びを豊かにします。いまの学校教育に最も欠けている『自分で選び/決めること』を前提にしていることもポイントです」
こう話すのは、杉並区教育委員会教育長付主任研究員で『教育は変えられる』の著者、山口裕也さんだ。
「教員主体の一斉一律の授業ではなく、『個別』に自分で選んで決めるからこそ、一生懸命頑張って試行錯誤し、もっと知りたいと『探究』に没頭していく。没頭するからこそ、壁にぶつかったときには真剣に困り、誰かと一緒にやりたいという『協同』の姿勢が内発するんです」





































