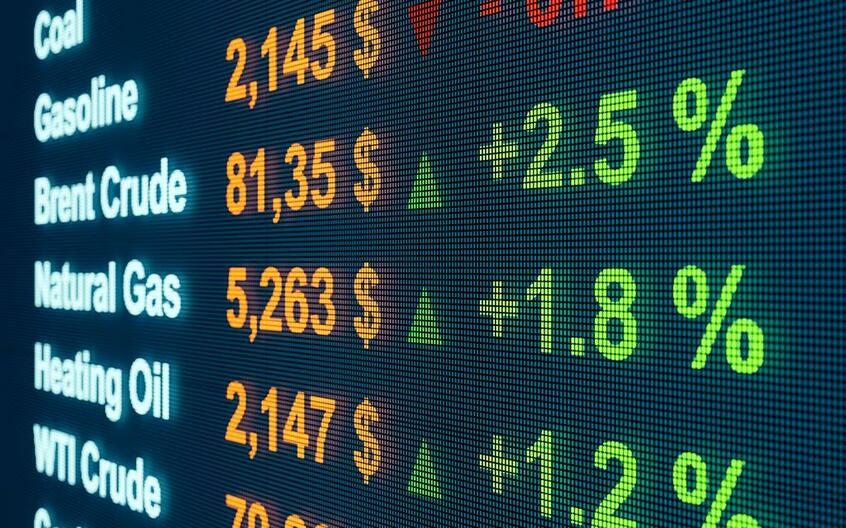
値上がりが顕著なのは生鮮魚介で、10月は前年同月比16.0%上昇した。水産庁によれば、卸売業者への平均販売価格が前年より約1.5倍に達しているという。その一因は漁船の燃料費の高騰だ。穀類も8.2%、生鮮野菜も6.7%アップ。電気代は20.9%、ガス代も20.0%上昇した。
物価の上昇を踏まえて政府が光熱費の負担を軽減する措置を打つのも確かだ。
具体的には、ガス代が1立方メートル当たり30円、電気代が1キロワット時当たり7円が補助される。2人暮らしの世帯では月330キロワット時前後が電気の標準使用量と言われており、そのケースなら2310円が補填される。
だが冬場は年間で最も光熱費がかさむ。
なぜならエアコンで33度の室温を27度に冷やす際の温度差は6度。これに対し、3度から20度まで暖める際の差は17度になり、その分だけ必要となるエネルギーが増すからだ。
これらの支出を真っ先に抑えたいところだが、日常生活に直結するので削りにくい。これが「悪いインフレ」とも言われるゆえんだ。
とはいえ、なるべく生活費を抑えつつ、できるだけ手元の蓄えも増やしておきたいと考えるのが自然だろう。
ただ、定年を迎えて現役時代より所得が減ったり、完全に年金暮らしだったりする家庭では、決してたやすいことではないと藤川さんは言う。
「通常なら、リタイア後の家庭では蓄えを取り崩しながら生計を立てるパターンになっているはずです。逆に蓄えを増やすとなれば、その分だけ出費を抑制する必要が生じますが、現役世代の家計と比べると、難易度が高くなります」
■22万円の1割を投資に回そう
総務省「家計調査報告(家計収支編)2021年」に掲載された消費支出の内訳によると、そもそも現役世代の家計では約18万円の黒字が出ており、特に節約しなくても貯蓄や投資に回す余裕がある。それもインフレで出費が増えれば、黒字幅が圧縮されてしまう。



































