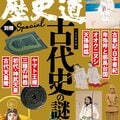この文書の宛所は、日蓮宗の僧である朝山日乗と明智十兵衛、すなわち光秀となっていた。これは、この条書が信長から光秀らを経由して義昭に突き付けられたこと、そして義昭がその内容を承諾する印を押したうえで再び光秀らに託したことを示している。
義昭は自分を京から追放した信長に深い恨みを抱いていた。光秀はその義昭の意を受けて本能寺の変に至ったのではないか。光秀を謀叛に走らせたのは義昭の指令だったのではないか――というのが、足利義昭黒幕説のあらましだ。
事実、元亀年間(1570~73)、義昭は京にあって「信長包囲網」を組織して以来、多くの武将に働きかけ、信長からの離反をそそのかしたり、信長への抵抗を促した疑いがもたれている。また、本能寺の変後に、光秀が発した文書や、義昭に関係する史料に、義昭が事件の背後にあったこと、光秀が義昭を将軍として推戴することを謀叛の大義名分としたとも解釈できる記述もみられる。
すべて義昭の指示で本能寺の変が起きたとする「黒幕説」は、事件以前に義昭が光秀に謀叛を命じていた直接の証拠がないために証明が難しいが、何らかの形で事件に義昭の存在が関わっていたとする余地はまだ残されているのではないか。
* * *
【黒幕説/検証 2】正親町天皇
■天皇は増長した信長の横暴を制止しようとしたのか?
正親町天皇は、後奈良天皇の皇子として永正十四年(1517)に誕生した。信長より17歳上になる。戦前の研究では、信長を勤王家ととらえるのが主流であった。戦後になると、正親町天皇との関係を、信長と足利義昭との関係に重ねて、当初の蜜月時代から、やがて対立へと向かっていったという解釈がなされてきた。特に室町時代研究の牽引車であった今谷明は、晩年の信長にとって最大の敵は正親町天皇であった。信長は翻弄され、ついには敗れ去った」とまで明言した。
この見解を受けて、以降、信長の行動や天皇観に危機意識を強めた正親町天皇、そして吉田兼見、近衛前久らの公卿が明智光秀を唆し、あるいは密勅を下すことで本能寺の変を引き起こしたと考える「正親町天皇(朝廷)黒幕説」が広がっていった。
この説は、信長と天皇(朝廷)が緊張関係にあったということを前提としている。その理由として、信長が天皇や朝廷に対しいくつもの圧力をかけていたことが挙げられている。その代表的な例は、(1)三職推任問題、(2)暦の改暦問題、(3)天正九年の馬揃え問題、(4)正親町天皇の譲位問題、以上の4点にまとめられる。