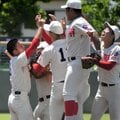――佳菜子さんが亡くなったことについて、後悔していることは?
妻はよく「子どもの半径3メートルより遠くに行けず、ずっと独りぼっち」「今日もぱっくん(朴被告)としか話さなかった」とこぼしていました。祖父母も近くにおらず、妻曰く「緊急避難ボタンがない」状態でした。私は週休3日、水曜は夜9時出社にして育児に加わりましたが、それでも妻に多く負担をかけていました。妻は子どもたちを強く愛していました。それは間違いありません。ただ私が頼りなかったのです。
妻の自死は私の責任です。育児休暇を取ればよかった。あの夏、ずっと妻のそばにいるべきだった。あの日、もっと早く家に帰ればよかった。子ども部屋に立てこもり続けてはいけなかった。
私は妻の話を聞けていなかった。そばに控えて背をさすっていただけでした。もっと妻に寄り添い、体調や気持ちについて話してもらう努力をしていれば、産後うつのことも打ち明けてくれたかもしれないのに。
また、カウンセリングを行う医療機関や障害を抱える子の親のサポートグループなど、第三者を頼るべきでした。無力なくせに、自分を過信していたのかもしれません。
――今、佳菜子さんを想うとき、どんな言葉をかけていますか?
子どもたちのことをよく話します。「通知表に優しくてユーモアがあるって書かれていたよ。みんな頑張り屋で頼もしい子で、君にも見てほしかった」というように。
妻は今も、立派で美しく愛しい人です。私が仕事のアドバイスを求めたら、いつも真剣に答えてくれました。家族みんなでたこ焼きを作ったことなど、思い出すことの多くは楽しかった場面です。
でも最後は「どうして死んだんだ」と考えてしまう。「老後の話もしたじゃないか。一緒にエジプトに行くって言ったのに。死なないでよ。たのむ」と。「一人で勝手に逝くなんてひどいよ」と妻を責める日もあります。そして「僕が守れなかったんじゃないか、阿呆が」と自分を責めます。