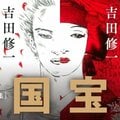野口さんが「高齢者こそリモートを」と唱える理由はそれだけではない。高齢者にとって最大の恩恵となる「遠隔医療」があるからだ。
「日本は後れを取っていますが、世界では医師が離れた場所から治療を行う遠隔医療が進んでおり、ロボット手術や、集中治療室の遠隔モニタリング(eICU)などが可能になっています。例えば高齢者が住む田舎町で脳卒中を起こして地元の病院に運ばれた患者について、センター病院の神経科の専門医が診断・治療の指示を出すことが可能です。こうした遠隔医療の波はいずれ日本にも訪れてほしいものです」
現在、オンライン診療は先進国では当たり前になっている。最先端の米国では、2020年の1年で10億回利用された。医師不足の中国でも遠隔医療は急成長している。
「日本では定期健診でも病院に行き、長い時間待たされる。コロナ禍ではそれだけで感染リスクが高くなってしまいます。オンライン診療ならそんなことはありません。また、医療の地域間格差も解消できるのに、日本が後れを取っているのが残念です」
オンラインを利用すれば、退職後の起業も容易になると指摘する。野口さんは大学に在職中から大学の研究室のほかに都内にオフィスを準備していた。だが、維持するには費用もかかる。
「リモート会議が主流になった今は必要ないと感じるようになりました。オンライン会議はコロナ禍前でも技術的には可能でしたが、オンラインでの打ち合わせを希望すると『会うのが嫌なんですか?』と聞かれたことがありました。今はほとんどの人が受け入れてくれます。これはありがたい変化で、私はコロナがもたらした唯一のメリットだと思っています」
オフィスや組織に依存せずに仕事ができれば、現役時代のスキルや特技を生かした独立・自営へ向けた動きも加速する。
「ヨガのインストラクターだってリモートでできる。以前と比べてビジネスを起こすハードルが低くなっているのは明らかで、何歳になっても働ける可能性は高くなっているのです」