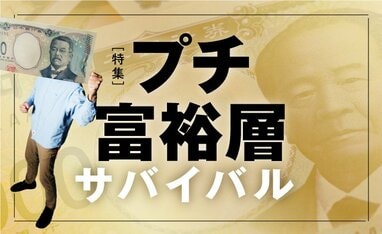先生の気持ち次第で点数がつけられてしまうことがあるならば、もし先生に何か意見したい気持ちがあったとしても、内申点を下げられることを恐れて、グッとこらえて我慢する子も出てくるでしょう。ある意味、みせかけばかりのいい子をつくることにもなり得ます。これでは息の詰まる学校生活になってしまうと思いませんか。中学という自己を形成する大切な時期に、本当の自分を抑え込み、先生の前でいい顔をすることを覚えさせてしまっているとしたら、いかがなものでしょう。
三つ目の理由として、内申点は、テストの点数や提出物で「失敗」していないこと、「いい結果」を出し続けたことを重視している点が挙げられます。
スタンフォード大学の心理学者であるキャロル・S・ドゥエック教授のベストセラー『マインドセット「やればできる!」の研究』では、子どもに対して、結果ばかり評価して、過程を軽視することを危惧しています。
■失敗を恐れずチャレンジすることが重要
点数ばかり重視すると、「結果がよくなければ評価されない」という価値観が強くなります。そして、「悪い点数を取るような『失敗』は許されないものだ」と考えます。すると、挑戦することをためらう人間になっていくのだそうです。失敗しない唯一の方法は、挑戦しないことだからです。
それに対して、努力するという過程を重視された子どもは、さまざまな困難に積極的に立ち向かうようになっていくそうです。過程を褒められるならば、何かにつけ頑張ろうという気持ちが湧いてくるものです。たくさん努力することにより自然と能力が伸びていく、というわけです。
内申点は、勉強の過程よりもテストで結果を出し続けた生徒のほうが高く評価されがちです。これでは、今後生きていくうえでも、「挑戦を恐れる」考え方に陥ってしまわないか、心配です。大人になってから重要なのは、失敗を恐れずにチャレンジしていくことです。
このような点を考えると、「内申点」にここまで重きをおくのは、少し考えものかなと思ってしまいます。