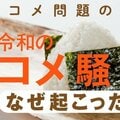苦肉の策として、同市は7月22日から地下水をくみ上げ、道路に埋設された消雪パイプに流し始めた。冬の間、雪を溶かすための施設で、道路から側溝に落ちた水が水路に流れる。しかし、消雪パイプの水が流れ込まない水路もある。笛木さんの水田の水路もそうだ。
「少しでも田んぼに水を入れようと、給水車(散水車)の貸し出しをいくつかのリース会社に問い合わせましたが、すでにどこも出払っていて、無理でした」と、笛木さんは肩を落とす。
だからこそ、実は、給水車は喉から手が出るほど欲しいのだ。だが、それがうまくいかないだろうことを、現場に近い人間は身をもって知っている。
あまりに米作りを知らない
小泉農水相は6月、こんな発言もしていた。
「米農家は2000万円のコンバインを1年のうち1カ月しか使わない。買うのではなくてレンタルやリースがサービスとして当たり前の農業界に変えていく」
この発言も、農家には「荒唐無稽」と受け止められた。同じ地域であれば、稲を刈り取る繁忙期はどの農家も同じなので、多くのコンバインを用意する必要がある。事業化は困難で、今春、JA三井リースが大型コンバインの貸し出し事業から撤退したばかりだ。
「コンバインにしても、給水車にしても、必要とする人の数に対して、台数があまりにも少ないので、実際にはうまくいかない。多少なりとも米作りを知っていれば、こんな発言はできないでしょう」(笛木さん)
2年前の「悪夢」再び
笛木さんが思い出すのは、2年前、2023年の夏の猛暑の悪夢だ。このときも、水田が干上がった。水を入れたタンクをトラックで田んぼに運び、水を撒いたものの、「一部の土が湿った程度」。
「なんとか収穫できた米も、猛暑による『高温障害』で、出来がよくありませんでした」(同)
23年、笛木さんは作付面積を3ヘクタール増やしたにもかかわらず、約100万円の減収になった。米の一大産地、新潟県全体でも高温障害による被害は甚大で、なかでも作付面積の6割以上を占めるコシヒカリの同年産1等米比率は4.9%と、平年の約15分の1と激しく落ち込んだ。
今年の米の出来はどうなるのか。
「通常、この時期に稲穂が出るのですが、水が干上がった田んぼでは出穂(しゅっすい)が遅れている。実が入らない『不稔(ふねん)』にならないか、心配です」(同)