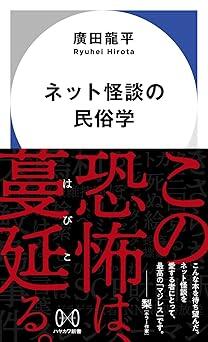
古くから本やテレビ、漫画などで誰もが一度は見聞きしてきたであろう「怖い話」。21世紀になって大きく変化したのは、怪談が生まれる場としてインターネットが台頭したことです。ネット民を震え上がらせてきた怪異の数々を、民俗学の概念から分析したのが、廣田龍平氏の著書『ネット怪談の民俗学』です。廣田氏は「本書の大きな目的は、一九九〇年代末から二〇二〇年代前半までのおよそ四半世紀にわたって、日本のネット怪談の大まかな見取り図を提示することである」(同書より)としています。
インターネット上で構築された怪談の中でも代表的なもののひとつが、2022年に映画化もされた「きさらぎ駅」ではないでしょうか。深夜、ある女性が電車に乗っていたところ、聞いたことのない「きさらぎ駅」に到着し、降りてみたものの、その後、消息不明になったというのが一般的に知られている話です。文章だけ見れば従来の怪談本などにもありそうですが、「はすみ」と名乗る本人の投稿をはじめ、多くの人々がリアルタイムで、あるいは数年を隔てて、別のメディアも駆使しながら、主要部分がオンラインで共同構築されていった点に、新しさがあると言えます。
これは1999年に「2ちゃんねる」の「オカルト板」が登場したことも大きいそうです。トピックごとに掲示板を用意することで、何百もの話題を同時並行的に進めることが可能になったため、異常な状況をリアルタイムで報告する「実況型怪談」が生まれたと廣田氏は分析します。ほかにも多種多様な実況型怪談が展開されることとなりました。
また、「くねくね」や「コトリバコ」「ヒサルキ」のように、地方の伝承にからめた民俗学風味の作品に対し、「2ちゃんねる」のスレッドで「自分も似たようなものを見たことがある・体験したことがあるという報告を続々と投稿していった」(同書より)という「連鎖型怪談」が生まれたのも、ネットならではの興味深い展開だそうです。
このように、序盤だけ見ても実に充実している同書。民俗学とは「教科書に載るような社会や歴史の大きな動きを見ているだけだと取りこぼされてしまう、多くの人々の言動や習慣(まとめて『民俗』や『伝承』などという)を研究する学問」(同書より)であることを考えると、ネット怪談との親和性が非常に高いと言えます。最終章では、最先端ともいえる「画像生成AIの怪談」も取り上げられ、今後のネット怪談の可能性についても論じられています。まさに、ネット怪談のデータベースのような一冊。現代の「恐怖」はどのように変化しているのか、興味をそそられた人はぜひ同書で確かめてみてください。
[文・鷺ノ宮やよい]


































