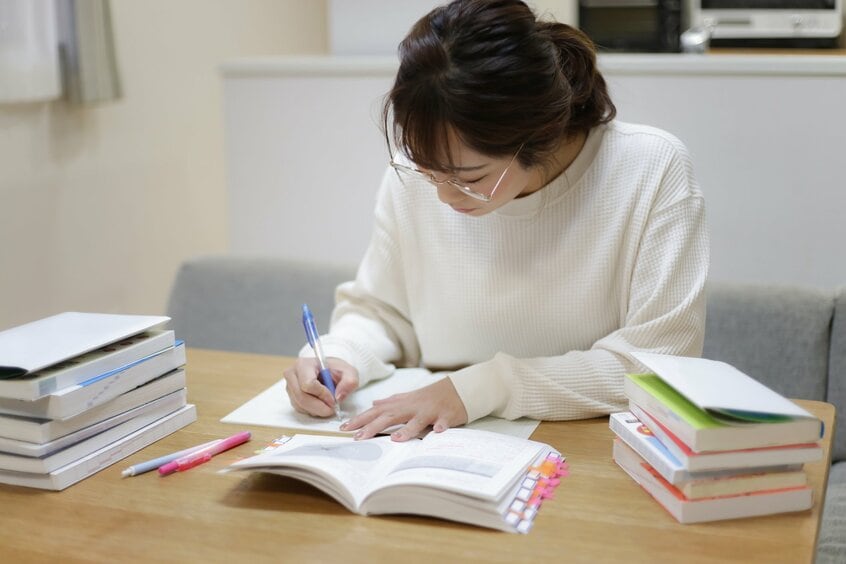
勉強といえば、本を読む、講義を聞くといった「インプット」が大事だと思いがちだ。一方、700回を超える講演・セミナーを開催して10万人以上に講義をしてきた精神科医の樺沢紫苑さんは、脳に刺激を与え、学んだことを記憶に残りやすくするためには、書く・話すといった「アウトプット」が重要だと指摘する。新刊『勉強脳』(サンマーク出版)より、「書く」ことの勉強効果を紹介する
* * *
なぜ「書く」と記憶に残るのか?
アウトプットとは、運動神経を使って、筋肉を動かすことです。手の筋肉を動かして「書く」。口や喉の周りの筋肉を使って「話す」。いずれも筋肉を使っています。
体を動かして覚える記憶は、「運動性記憶」と呼ばれますが、運動性記憶には、一度覚えるとその後はほとんど忘れることはないという特長があります。
3年ぶりに自転車に乗ったら、自転車の乗り方を忘れていた、ということは、絶対にありません。同様に、ピアノを弾くこと、ブラインドタッチなど、反射的な、いわゆる体で覚えるような運動技能は「運動性記憶」として記憶されているのです。
『図解 大学受験の神様が教える 記憶法大全』(和田秀樹監修、ディスカヴァー・トゥエンティワン)には、「筋肉や腱を動かすと、その運動は小脳を経て、記憶の中枢・海馬に伝えられ、大脳連合野に蓄積されます。運動性記憶は、このように多くの神経細胞が働くことで脳に残りやすくなる仕組みになります」と書かれています。
「丸暗記」は、「意味記憶」を使って記憶しますが、「意味記憶」は覚えにくく、忘れやすいという性質があります。そこで、「書いて覚える」「声に出して覚える」ようにするだけで、「運動性記憶」として記憶することができるのです。

※価格などの情報は、原稿執筆時点のものになるため、最新価格や在庫情報等は、Amazonサイト上でご確認ください。





































