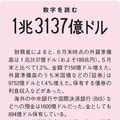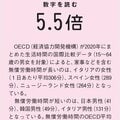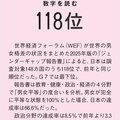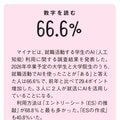人口が減少する日本において、東京都の人口はこの30年で250万人増加し1400万人を超えた。一極集中にも問題はあるが、投機目的で空室のまま放置されるマンションが増えれば、本来の再開発の意義も損なわれてしまう。今後、このような規制は増えていくだろう。
海外では、こうした問題に対し「空室税」を導入している。カナダでは、年間6カ月以上空室のままだった物件に固定資産評価額の1%程度を課税しているという。日本でも検討する価値があるだろう。
以前、このコラムでも外国人による不動産購入が価格高騰の原因だと指摘したことがあった。しかし、先日の参議院選挙で外国人排斥につながりかねない言説があったのを見て、反省した。安易に「外国人」と一括りにすることの危険性を感じたからだ。
「外国人」という言葉には、多様な背景が含まれる。たとえば、日本に長年住み、地域社会の一員として働き続けている外国籍の方も多くいる。こうした人々を単に「外国人」として規制の対象にするのは公平ではない。
外国人による不動産投資が価格高騰の原因の一つになっていることは事実だが、重要なのは、「外国人かどうか」ではなく、「居住実態の有無」や「投機目的の購入かどうか」だ。
規制すべきは「空室のまま放置される物件」や「短期的な転売を目的とした取引」なのだ。
席取りで埋まったフードコートや、空室が目立つマンションを見るたびに、この社会が誰のために、どのようにあるべきなのかを考えさせられる。「誰もが安心して暮らせる街づくり」を目指すために、私たち自身が見つめるべき問題は何なのか、改めて問い直す必要があるだろう。
※AERA 2025年8月4日号
こちらの記事もおすすめ 「子どもに資産運用を勉強させないと」 親が抱く“金融教育”の誤解 より大切なのは「働いて稼ぐ力」 田内学