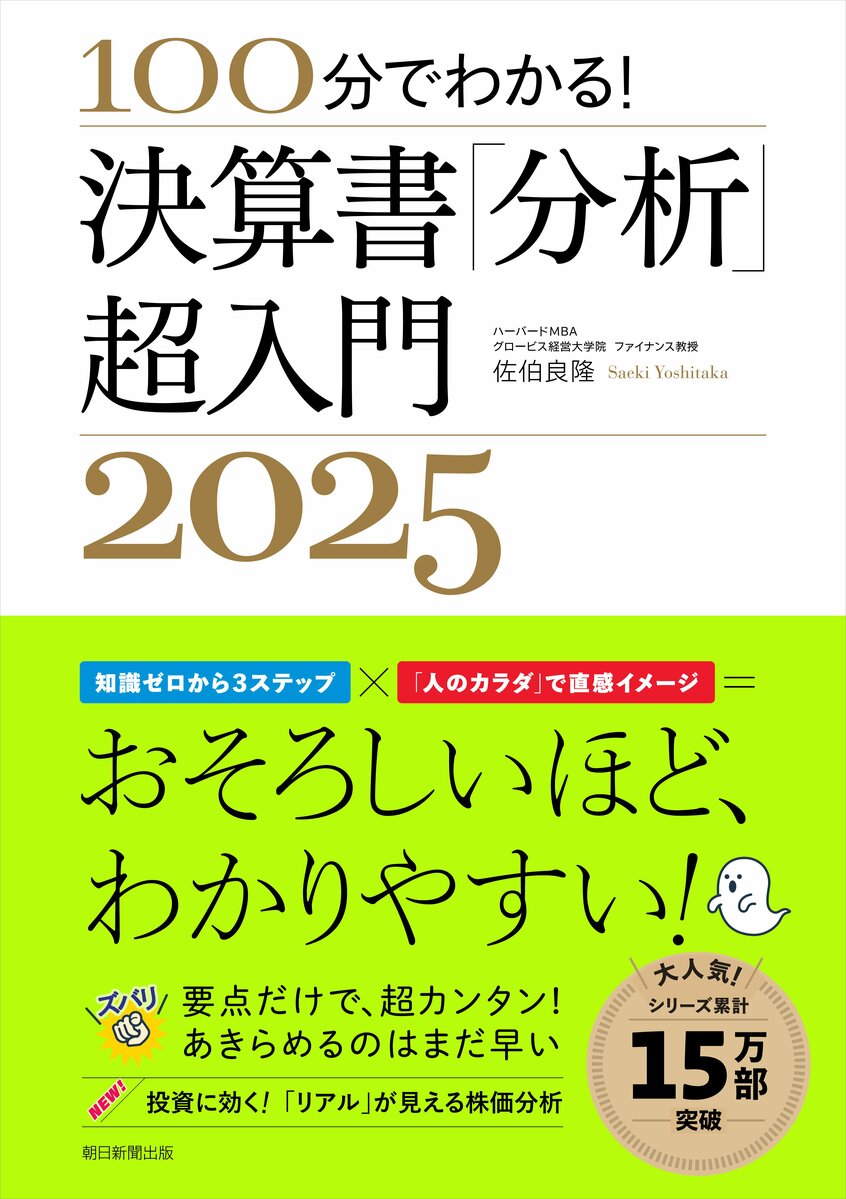つまり自己資本の大きさを考えることは、他人資本である負債の大きさを考えることとイコールであり、自己資本の割合が大きいほど負債は小さく、自己資本の割合が小さいほど負債は大きくなるといえます。
このような資産における負債の依存度(活用度)のことを、専門用語で「レバレッジ」といいます。レバレッジとは、「てこ」という意味です。これは自分の力(自己資本)が小さくても、てこ(負債)を利用することで、重いものでも動かせる(事業を拡大できる)ことからきています。
ROEをみるときは自己資本の割合も確認する
ここまでの話をまとめましょう。ROEの「自己資本→資産→売上→利益」の流れを数式に置き換えると、「ROE=レバレッジ(資産÷自己資本)×ROA(総資産回転率×売上高利益率)」となります。
こうしてみると、ROEの高さは、ROA(経営活動の上手さ)だけでなく、レバレッジの高さ(負債の大きさ)にも左右されることがわかると思います。つまりROAに関係なく、借金が膨らめば膨らむほどROEの数値は自然と高まってしまうのです。
このように、ROEが高まっている裏に、財務の安定性が損なわれている場合があるので注意が必要です。
もちろんレバレッジが悪いというわけではなく、負債を上手に活用することで順調に事業を拡大している会社もあります。ROEの上昇が、総資産回転率、売上高利益率、レバレッジのどこからくるのか、その要因を分析することが重要なのです。
《好評発売中の書籍『決算書「分析」超入門2025』では、ROAとROEの関係について、図を用いてさらにわかりやすく解説しています》