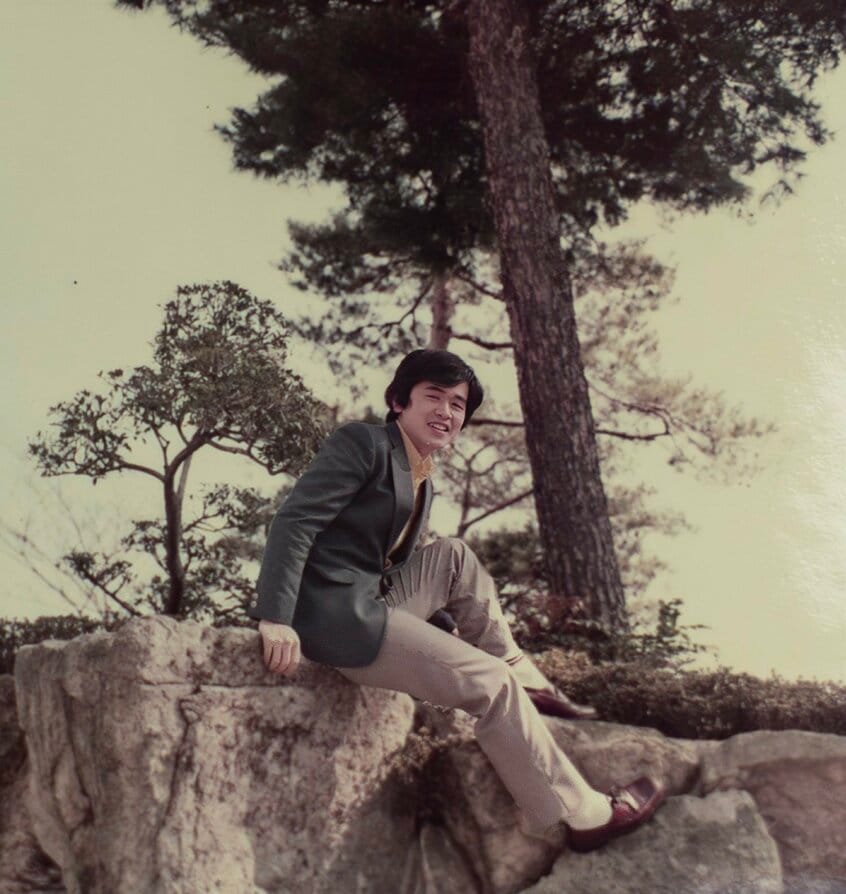
小学校の学友たちが目指す進学校でなくのんびりした校風へ
1956年2月、西宮市の阪急電鉄の西宮北口駅近くで生まれる。父は建設会社に勤め、母と弟、妹、祖母の6人家族。幼稚園のときに父が独立して建設会社をつくり、宝塚市の逆瀬川駅近くへ転居した。通った宝塚第一小学校の通学圏に大きな会社の社宅がたくさんあり、どの親も教育熱心で、中学校は私立の進学校へいく児童が多かった。それとは距離を置き、のんびりした感じの関西学院中学部がいいなと思い、受験する。
中学部では硬式テニス部へ入って毎日、遅くまで練習した。学友は「お坊ちゃん」というタイプが多く、大半はそのまま関西学院の高等部へ進む。でも「それでは物足りない」と思い、高校進学も自分で考えた。調べると、県立高校には内申書を中心にみて、試験は知能テストみたいなだけの方式がある。「受験勉強をしていなくて何とかなるか」と思い、名門の県立神戸高校へ願書を出すと受かった。
「自分で考えて決める」という高校進学だったが、大学は多くの級友が目指す京大を、「何となく」受けて落ちて、橋本流を取り戻す。予備校へいって東大の過去の入試問題をみて、暗記したことを一問一答で進めるのではなく、論ずる出題傾向が「自分に向いている」と思い、勉強内容を東大受験向けへ変えた。
75年春、東大文科II類に合格。ビジネスの世界へ進むつもりだったので、経済学部が念頭にあった。高校時代に本で映画と演劇の違いを読み、「演劇のほうが真剣勝負で面白い」と思っていたので「大学へ入ったら演劇をやろう」と決めていた。東大演劇研究会へ入り、舞台に立ったり脚本や演出を担当したりするのではなく、裏方を続けて、組織運営を経験する。
就職先は、性格からみて商社マンに向いていると思い、ビルを建てて貸す大手不動産もいいな、と考えていた。10月1日の採用活動解禁日、東京・西新宿で空き時間ができて、「三角ビル」の住友生命にいたゼミの先輩のところへ寄った。すると、「昼ごはんを食べていけ」と言われたが、商社の面接時間が迫っていたので、辞退して出た。





































