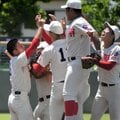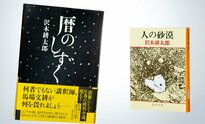まずこのドラマの舞台であるそば店「大正庵」の場合、従業員は、蕎麦職人やフロア係、洗い場担当、そして出前スタッフなど、総勢10人ほど。そんなに大勢が働いていながら、店内で鳴り止まない出前注文の電話をさばききれず、かかってきたクレームの電話に「もう出たと言っておけ」という「蕎麦屋の出前」的なセリフがドラマ内に出てきた記憶がある。
知らない世代のために説明すると、まだ出発していない出前を、「たった今出ました」と言って客をなだめるアレのこと。ちなみにライターの自分は、実際はまだ原稿が100行以上残っているのに、「あと5行で完成です」という「蕎麦屋の出前」的な言い訳をすることが、今もよくある。
出前受難の時代に
昔ながらの商店街で古くから営業している「楓庵」(東京都新宿区)の3代目店主、山田茂さん(72)も、日本が高度成長期だった頃のお蕎麦屋さんの様子を、こう振り返る。
「会社や家庭から店に足を運ぶお客さんに加えて、出前も多かったですよね。出前の従業員だけで2~3人いたこともあるほど。それでも年末など、企業から天ぷら蕎麦150杯などの大量注文が入って、出前に何往復もしたことがありました」
昭和30~40年頃のものと思われる商店会のチラシを見てみると、楓庵は「冷むぎ60円」「あんみつ35円」といった、蕎麦以外のメニューをアピール。この頃、今もよくあるラーメンやカレーライスなどグローバルな蕎麦屋メニューはすでに登場して、当時の町のお蕎麦屋さんを、家族みんなが楽しめる「昭和のファミレス」とか、安い!早い!うまい!で小腹を満たす「昭和のファストフード」と呼ぶ人もいる。
ところがバブル崩壊など、景気の減速が明らかになった2000年前後から、残業する人も減って、夜食需要が激減する。同時に企業の出入りが厳しくなったほかオートロックのマンションも増え、蕎麦の出前はもちろん、器を下げるのも簡単にはできない出前受難の時代に。
楓庵の場合、すでに長男が4代目に手を挙げてくれているが、とくにコロナ以降はどこにも寄らずに帰宅する人も増えて、夜の営業をどう成功させるかがネックになっている。建物の老朽化もあり、現在思い切って店内を全面改装中だ。(ライター・福光恵)
※AERA 2025年4月14日号より抜粋