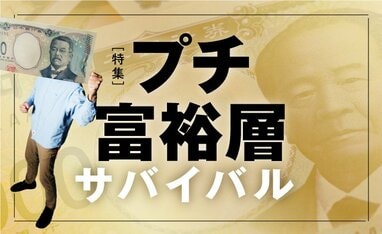社会問題と向き合う日高屋経営
CSVは2011年にマイケル・ポーターとマーク・クラマーによって提唱された概念であり、社会問題の解決と企業の収益拡大を同時に実現する経営戦略とされている。CSR(企業の社会的責任)とは異なり、CSVは本業と密接に結びついた取り組みである。
ポーターらはCSVの実現方法として、3つの方向性を示している。平易な言葉でいうなら、以下のようになる。
(1)困っている人のための商品やサービスをつくる
(2)仕事のやり方を工夫して効率を上げる
(3)地域と協力して仕事がしやすい環境をつくる
たとえば、出所者を積極的に受け入れ社会復帰を支援する「新宿駆け込み餃子」や、耕作放棄地を茶畑に再生させることを支援する伊藤園などは、CSVの良い例である。
日高屋もまた、社会課題に向き合いながら経営の基盤を強化してきた企業である。人手不足、高齢化、外国人労働者の受け入れといった課題を前向きに捉え、それを人材活用の機会へと転換してきた。現在も84歳の現役会長として第一線に立ち続ける神田正氏の姿勢からは、企業がどうあるべきかという問いに対する一つの答えが見えてくる。
日高屋は、価格や味だけで語られる存在ではない。働く人にとっての「居場所」を提供し、地域にとっての「生活の一部」となっている。人を活かし、社会とともに歩むこの外食チェーンは、CSV時代における新しい成長モデルとして注目に値する。
(小倉健一:イトモス研究所所長)