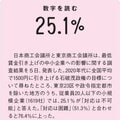大島 非人間化するんですよね。
小川 逆に言えば、相手が人間だと思った瞬間に、攻撃できなくなる。人間って、それぐらい共感力の高い生き物なんです。だからこそ、人格を否定をすることがいかに危険なことか、歴史や社会学から学ぶべきなんです。
松尾 やつはモンスターだってみんなで言えば、相手を叩くことへの罪悪感も軽減されますからね。むしろ世直しのために言ってるような気にもなれるんですよね。とはいえ、度を越した頑なさはいかんともしがたいもの。「この人の考えを変えることはできるかなあ?」と思うと茫然としますよ。
小川 変えることが目的じゃないんですよ。なぜそう考えるのかを理解すること。それが到達すべき目標地点なんです。
松尾 お説ごもっともですが、相手の頑なな部分を少しは変質させないと、伝わるものも伝わらなくないですか?
和田 私もそう思います。
小川 相手を「頑なだ」と思っている、その自分は頑なではないですか? っていうことですよ。これって、ひとえに思考の訓練、修行なんです。
松尾 思考に柔軟さや弾力性を与えることと、信念として筋を通すというのは似て非なるもの。肝心なのは両者をどう両立させるかではないでしょうか。
小川 そうそう、だから、相手を変えられないからといって、自分も変わる必要はないんです。
人間をどこまで信用できるか、という問いにもかかわるんですけど、相手がどんな主張をしていても、必ずそれには理由となる背景があるので、そこを信用してあげる。かなり高度なことだとは思います。
たとえば、個人名は避けますけども、自民党に右翼屋さんはたくさんいます。でも、筋金入りの右翼だなと思う人はほとんどいないんです。
大島 そうですよね。その時々の立場や情勢に合わせて、そうなっていった人たち。もとは違ったはずなんだけど、右寄りの発言をしたらウケがよかったので、だんだんとそっちへと考えが変わっていった。
和田 言ってるうちにその気になるというのもあるのかも。相乗効果でどんどん変わる。
小川 票が欲しいですからね。
大島 票も欲しいし、エコーチェンバー的な、周りのウケがいいとほめられますからね。
小川 相手の考えの背景を理解すべきっていう趣旨には、それも含めてのことなんです。相手の考え方の根っこの部分に、利害や損得はないのか。
大島 でも、相手の背景が理解できたとして、じゃあその人にどう向き合うか、っていうのは次のフェーズな気がするんですけど。
小川 次のフェーズですよ。だからこそ相手が暴力的にならない限り、変えようと思う必要はない。
相手はなぜそう考えるのかって考えたほうが平和的で、自分も救われるんです。相容れない相手について「こんな人間がいるのか! 信じられない!」って思うこと自体が、呪縛であり、自分を苦しめるんです。
でも「そりゃそうだよな、人間、置かれる立場や利害で、そうもなるよな」と思えたほうが、自分にとっても救済になる。自分を解放するために、相手を理解する努力を最大限尽くす。それは究極、相手を人間として尊重するということにほかならない。