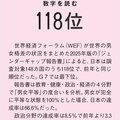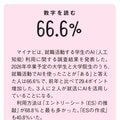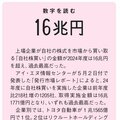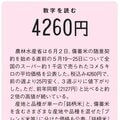問題はさらに根が深い。朝日新聞取材班の『8がけ社会─消える労働者 朽ちるインフラ』によると、なんとか予算を確保しても人手不足から工事を請け負う業者が見つからず、工事が進まない例が増えてきたそうだ。また、この本で、東京大学の金井利之教授が指摘するように、公共サービスやインフラを縮小する際の合意形成は、新たに整備するときよりはるかに困難だ。
しかし今回の事故が示すように、この問題はまるで“トロッコ問題”の様相を呈している。トロッコ問題とは、倫理学の思考実験の一つで、暴走するトロッコの軌道上にいる人を助けるために、特定の人を犠牲にしてもよいのかという問題のこと。今回の場合、放置すれば道路の崩落が起き、尊い命が失われるかもしれない。しかし、インフラを縮小しろと言えば、住民には生活様式を変える負担がのしかかる。その狭間で意思決定を先送りにしてしまっているのではないだろうか。
では、インフラをどう再編し、誰がどこに住み、どの範囲を維持していくのか。『8がけ社会』が示唆するように、2040年には生産年齢人口が現在の8割にまで減る見込みで、人手不足が本格化する前に真剣な議論が必要だろう。道路陥没が鳴らした“警鐘”を、一時的な事故として片付けるのではなく、社会全体で向き合うときが来ているのではないだろうか。
※AERA 2025年2月17日号