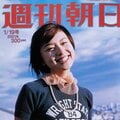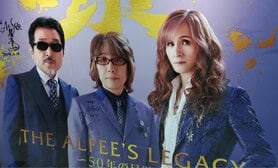深紅の薔薇を抱えて現れた三島由紀夫 美輪明宏 聞けなかった遺言
三島さんについて言えることは、あれほどの天才でも少年時代に受けた教育のトラウマからは一歩も逃れることができなかったということね。彼は非常に鋭利で理論派だから、一見、論理的に自己分析をしているように見えていたのね。私もそう思っていた。でもやっぱり、渦巻きには、渦巻き自身の姿は見えなかったんだなと思います。どう流れていっているのかがね。
私と三島さんとの親交は一九五一年、小説「禁色」の舞台にもなり、当時私がアルバイトをしていた銀座のバーで出会ってから。それから、シャンソン喫茶「銀巴里」のステージを見に来てくださったり、六八年には大ヒットした三島さん脚本の舞台「黒蜥蜴」に私が主演するなど、彼が死ぬまで続きましたね。
三島さんと待ち合わせをすると、私がどんなに早く行っても、必ず彼が先にいるわけですよ。つまり、人を待たせるというのが嫌でね、待っているほうがいいという人だった。まったく、第二次世界大戦前の「日本少年」や「少年倶楽部」などの少年雑誌に出てくるような人だった。儒教じゃないけれど、君に忠、親に孝というような模範的で道徳的な、心優しくすがすがしくというような、少年のいちばんいいころの心を持っていた。男が社会的ないろいろな手あかがつく以前の、少年の心をあの年になるまで持ち続けていた人なんですよ。
彼には文壇向きの、営業用の「顔」というのがありましたね。尊大ぶらなきゃいけないとか、作家ぶらなきゃいけないとか。そうしないと、なめられちゃうんですよ、出版社などの人たちに。そういう駆け引きなんかはおできでしたね。そうした人たちが帰った後では、おどけちゃって、首をすくめて、ぴょんと舌を出したりして。まったく子供みたいでしたよ。
「自分は文学界には友達はいない」
とおっしゃっていました。
三島さんと最後に会ったのは、自決する一週間ほど前、あの人が大好きだった日劇の楽屋でした。珍しくたった一人で、正装で現れたんです。抱えきれないほどの深紅の薔薇を抱えて。メーキャップをしていたら、鏡越しに暖簾の向こうにズボンとエナメルの靴が見えたんです。「だれ?」と叫ぶと、「三島です」とゆっくり入ってきた。珍しくプライベートなことを話しました。きっと、これから自殺することを気づいてほしかったんだと思います。あのとき気づいていれば。
そしてあの日、知人から舞台寸前の私に電話が入ったんです。テレビをつけると、三島さんがバルコニーで演説している最中だった。とうとうやったかと思いましたね。
いま、三島さんは生きていなくてよかったと思いますよ。こんな時代を見なくてすんだから。
「文豪は年を取ってから世紀の傑作ができるときもある」
と言ったら、彼は、
「自分は嫌だ」
と言いました。
「床柱を背にして、紬の着物を着てふんぞり返っているようなのは、俺には似合わない」
とね。(談)