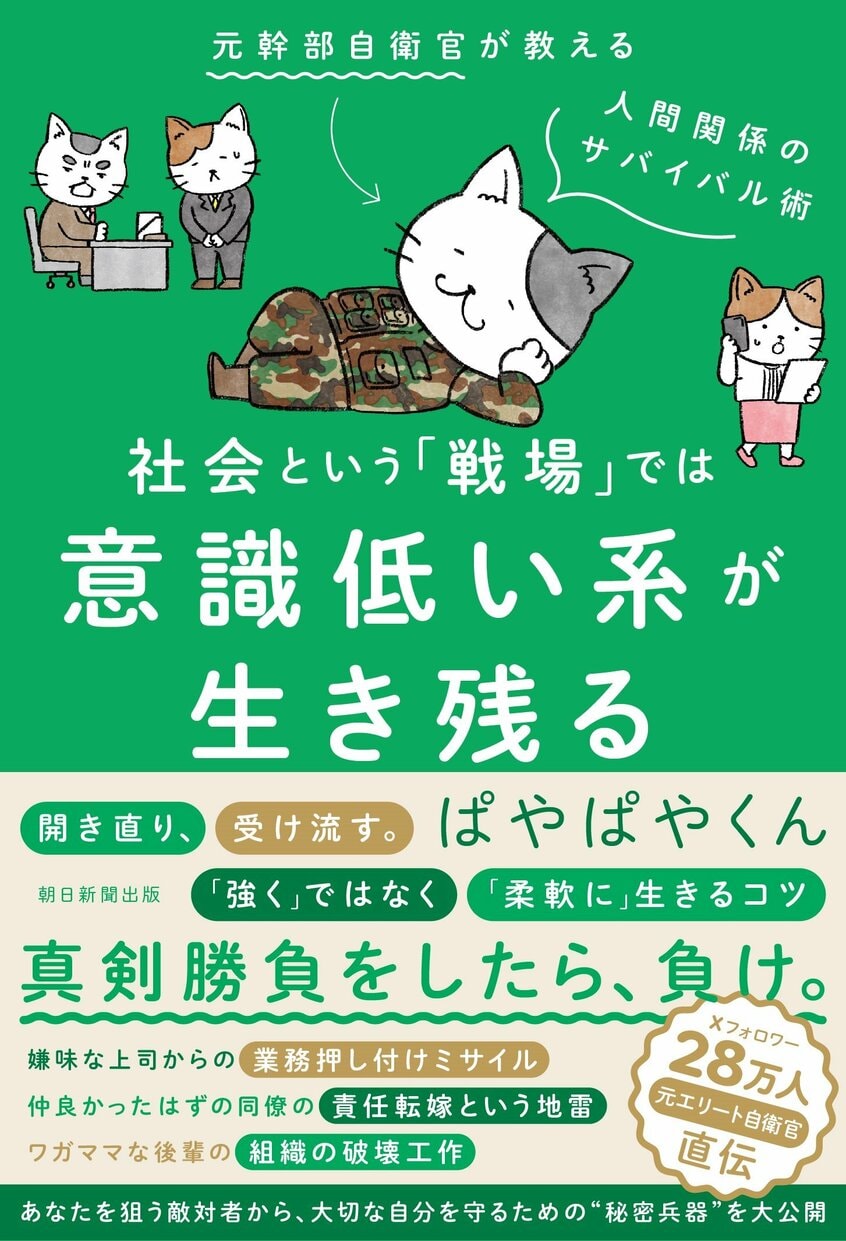
「真剣」と「適当」の切り替えができる場面は、日常生活の中にたくさん潜んでいます。たとえば、車を運転しているときに、最大限の集中をするようにしますよね。ただ、後部座席に座っているだけのときには睡眠をとるようにするのは、モードの切り替えの例として、非常にわかりやすいと思います。
その他、適当モードで生きていていい場面は、意外と日常生活の中にもたくさん潜んでいます。「嫌なことがあったときはランニングをして汗をかき、熱い風呂に入って早く寝る」「嫌な上長の指摘を真に受けない」「嫌な先輩はとりあえずヨイショをする」「細かいミスを指摘されても、人間だからしょうがないと考える」など、「深く考えない」「力を抜く」ということを意識していきましょう。
仕事や生活で、体力的・精神的に負荷が大きいものこそ、リラックスを意識しないといけません。
むしろずっと「真剣モード」で動いている人は、疲れやすく、気力も回復しにくいです。そのため、作業も滞りがちになることさえあります。すると、皮肉なことに、最終的には「適当な人」というジャッジを受けやすくなります。
このような状況はできるだけ避けたいですよね。そこで、ここでは、ちょうど良いという意味での「適当」になる方法を、具体的にいくつかお伝えします。
1、暖かい地域に行く
沖縄県民にはおおらかな人が多いと言われます。
その理由の一つに「真剣に考えるには、沖縄があまりに暑すぎる」という説があるのは知っていますか。
暑い気候では頭がぼんやりします。そして疲労も蓄積されてしまいます。
だからこそ、ある程度のところで妥協をして、「なんくるないさ〜(なんとかなるさ)」の精神で生きていく必要があるんじゃないかと私は考えています。
暖かい地域には「なんくるないさ」に似たような言葉がよく使われています。
宮崎県には「てげてげでいっちゃが〜(適当でいいよ)」というのがありますし、タイには「マイペンライ(大丈夫)」、香港などでは「モーマンタイ(大丈夫)」、ラオスは「ボーペンニャン(気にしなくてもいいよ)」と「気にしないこと」を勧める言葉がたくさんあるのです。
たとえば、タイに行くとわかりますが、何でもかんでも「マイペンライ」で済ませようとしてきます。ホテルの部屋が水漏れしていても「マイペンライ」、時間に遅れていても「マイペンライ」で終わりです。
東京で「大丈夫」と連発しているといつか怒られるかもしれません。でも、帰り道に「モーマンタイのボーペンニャン」と呪文のように唱えてみてください。
なんだか、ちょっと適当になれた気がしませんか。



































