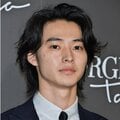「同年代は割と積極的に取り組んでいたけど、私は元々けんかは好きじゃないし、早く家族のところに帰りたいなと思っていた」
だが、結局、兵役を347日延長した。理由は「家族のため」。必要な知識を身につけ経験を積み、有事に備えておきたいという気持ちが強くなったという。「国を守ることが、家族を守ることだと痛感したんだ」
フィンランドの人々の中にある、国防意識を感じた瞬間だった。
徴兵制というと、日本に暮らす自分はつい「苦役」と身構えてしまう。だが、取材で会った若い兵士たちは、「兵士になるのは使命だと思っていた」と口をそろえた。
徴兵制とは別に、軍の予備兵の軍事訓練や、日々の安全や非常事態への対応方法を教育する国家機関、フィンランド国防訓練協会(MPK)も存在する。
街中にシェルター
コロナ禍を境に軍事訓練を志願する国民は減っていたが、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに増加に転じ、23年は20年と比べ2倍以上になった。銃の使い方、キャンプの設営方法、応急処置の仕方などを学ぶ女性向けの講座は、順番待ち状態だ。
同国国防省が2022年5月に実施した世論調査によると、フィンランドが攻撃された際、「祖国防衛に参加する」との回答は実に82%に上った。
フィンランドには、街中いたるところにシェルターがある。ヘルシンキ中心部メリハカ地区の公共シェルターは、地下およそ20メートル、岩盤をくりぬいたような巨大な空間だ。普段は、地下通路や、ジムやフットサルコート、駐車場などとして使われているが、有事の際は周辺の集合住宅の住民ら6千人を収容するという。避難者は、シェルターの運営など労働、自由時間、就寝の3交代制で動く想定で、簡易の3段ベッドは2千人分用意してある。
アパートなどの集合住宅にもシェルターがあり、各家庭ごとに部屋が割り振られている。もしも建物が倒壊しても、シェルターは崩れることなく残る仕組みだという。