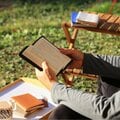教員の長時間労働が問題視されて久しいが、依然として多忙さが解消せず、苦しむ先生が後を絶たない。影響は、子どもの学びにまで及んでいる。『何が教師を壊すのか』(朝日新書)の著者が、現状を報告する。AERA 2024年4月29日-5月6日合併号より。
* * *
神奈川県の公立小学校の職員室。4年生の担任を務める30代男性教諭は、パソコンに向かっていた。時計を見上げると、午後6時。退勤時間を1時間以上過ぎていた。
子どもが下校してから、息つく暇も無かった。子ども同士のトラブルについて、当事者の家庭に電話で説明し、謝罪。運動会の準備に必要な作業についての打ち合わせ。遠足の書類づくりと手配のための電話かけ。子どもたちに配る予定表の作成と印刷。校内向け時間割の修正や印刷。テストの採点と記録。休憩はとれなかった。
この日は結局、翌日の授業の準備はできなかった。教員として一番大事なはずの授業がおろそかになっていると思う。
それでも、授業時間がやってくる。「次の国語、なにをやろうかな」。授業直前の5分休憩の際、職員室に戻る時間も惜しみ、教室で教師用指導書を開く。ぱらぱらとめくったあと、1分ほどで授業の組み立てを考える。教科書の文章を、授業中に子どもと一緒に初めて読んで内容を把握する。そんな「ぶっつけ」も少なくない。「子どもに申し訳ないけど、こんなもんです」
どうすれば授業に力を入れることができるのか。10年以上の経験がある先輩に「準備する時間がないんです」と相談してみた。「ずっとそうだよ、私も。まじめにやると、体を壊すよ」と返ってきた。
あるとき、同じ学校の若手教員が突然出勤しなくなり、退職した。男性は、この若手が遅くまで1人で仕事をする姿をよく見かけていたのに、余裕がなくて声をかけられなかった。「職場に絶望したってことなのか……」。苦い思いが残ったままだ。
関東地方の公立高校に勤める30代女性教諭はある夜、職員室でパソコンに向かっていた。この日は休みのはずの土曜日だったが、週明けの授業の準備が終わっていなかった。
平日は放課後、顧問を務める文化部の活動が毎日のようにある。夜までかかることもざらで、授業の準備に割ける時間は実質、土日だけ。だが、この日の午後は顧問を掛け持ちする運動部の活動があった。翌日の日曜日は、文化部の発表会の引率がある。