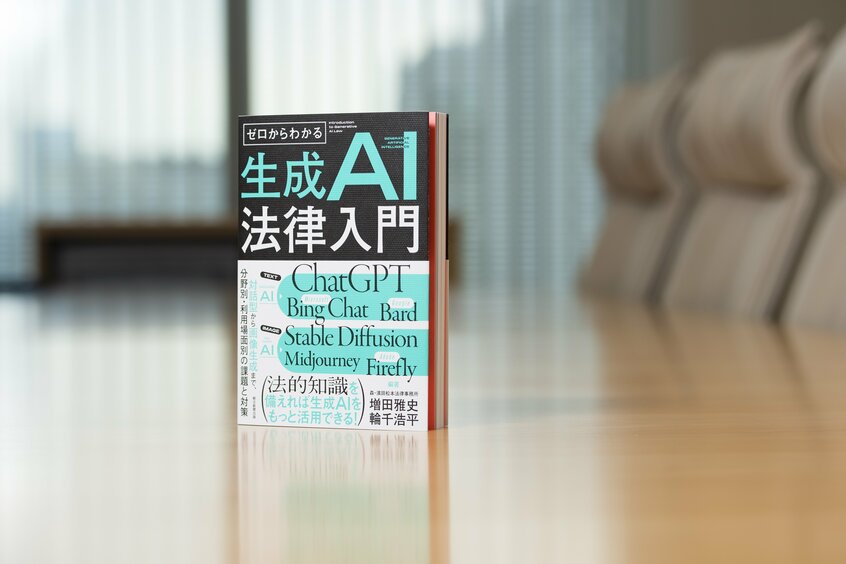
今年7月、バイデン大統領がAIの大手企業7社のトップたちと会談し、AIシステムについての自主的規制をすることに合意を取り付けました。ただ、この合意には法的拘束力はなく、現状は業界の自主的な取り組みに委ねているのが現状です。
ただ、生成AIに対する世論の警戒感は日本よりも強い。例えば、今年3月には、AI開発の一時停止を求める声明が、イーロン・マスクやAppleの共同創業者等から公表されたことも話題になりました。仕事が奪われる脅威だけでなく、AIが人類を超えるということに対する警戒感も示されています。今年5月にハリウッドで始まった米脚本家組合(WGA)などのストライキでも、生成AIの利用が大きな論争の一つであり、いまの時代をめぐる象徴的な紛争と言えます。
そして、既にアメリカでは、生成AIサービスを提供する企業に対して、著作権法違反やプライバシー侵害などを理由とした集団訴訟が続々と起こされています。たとえば、作家たちが、勝手に自分たちの著作物が収集され、生成AIの学習に使われ、著作権が侵害されたといった主張がなされています。
このようにアメリカでは、生成AIについて、既に紛争や個別の訴訟が大規模に発生しつつありますが、政府はAIの過度な規制についてはやや慎重な姿勢をとっているのが現状といえそうです。今後、連邦、州レベルでの法規制の動きや集団訴訟の動向など、追っていく必要があります。
ちなみにですが、英国政府は、AI規制については、EUとは違う路線をとろうとしており、“pro-innovation”(プロイノベーション)、イノベーションを積極的に促進する立場をとることを明確にしています。その意味では、EUよりは米国に近い路線をとっているといえるかもしれません。ブレグジット後、EUから離れた立場を利用して、EUほど厳しい規制をとらず、より柔軟な独自のポジションを構築しようとしています。
アメリカや英国が今後具体的にどのような法規制に着地するのかはまだわかりません。ただ、アメリカや英国のアプローチは、EUのAI法案による規制よりも、よりビジネス寄りのものになると言われています。





































