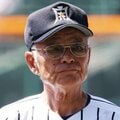夏の甲子園出場をかけた高校野球の地方大会も大詰めを迎えているが、今年大きな話題となっているのが相次ぐ強豪校の敗退だ。優勝候補と見られていたチームが敗れる度に新聞には『波乱』の文字が大きく踊っている。
【写真特集】「伝説の女子マネ」も登場! 増刊『甲子園』の表紙を飾った美少女たち
しかし改めて見てみると『波乱』という表現が適切ではないケースが多いことも確かだ。センバツ優勝の山梨学院は山梨大会の準決勝で敗れたが相手の駿台甲府はエースの平井智大(3年)をはじめ力のある投手を複数揃えており、昨年秋の関東大会にも出場している。またセンバツ準優勝の報徳学園も敗れた相手は県内で長年ライバル関係にある神戸国際大付であり、実力的には互角の相手だった。その他の優勝候補と言われながら敗退したチームを見ても、ほとんどの相手は力の均衡したチームである。
智弁和歌山を初戦で破った高野山は昨年秋、今年春も県大会で早々に大敗していることもあって確かに『波乱』と呼ぶにふさわしいのかもしれないが、ほとんどの場合はある程度予想できたケースであり、一発勝負のトーナメントであれば不思議はないと感じているファンも多いのではないだろうか。そういう意味では地方大会の“波乱”は勝手なイメージとマスコミによって作られたものが大半と言えるだろう。今後もそういう作られた波乱はあっても、本当の意味での波乱が続出するようなことはやはり考えづらい。
ただ一方で力が劣ると見られていたチームが強豪校と勝負しやすくなっている要因があることもまた事実である。一つはあらゆる意味で情報化が進んでいる点である。以前は環境に恵まれた強豪チームだけが先進的なトレーニングを行い、専門家による指導を受けることができていたが、現代ではどのチームもそういった情報を得ることが可能になっているのだ。また監督や常駐のコーチ以外の外部指導者、トレーナーに師事するケースも増えており、特にピッチャーに関しては強豪以外からもプロが注目する選手が出てくることが珍しくなくなっている。さらに来年からは低反発の金属バットが導入されることが決まっており、今後さらに“非強豪校の好投手”に強豪校が苦しむケースが増える可能性もありそうだ。