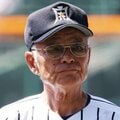また情報化に関しては対戦相手の分析という点でも大きな影響を与えている。今年夏の地方大会は「バーチャル高校野球」によって全試合がネット配信されていたが、以前と比べてもそのような形でチームや選手の情報を収集しやすくなっている。前年秋から結果を残しているチームはそれだけメディアで取り上げられることも多く、対戦相手に事前に情報を多く提供することになる。
2018年のセンバツに21世紀枠として出場した膳所は野球経験のない部員が分析担当として大胆な守備シフトを用い、実際にヒット性の打球をアウトにしたことでも話題となったが、こういったプレー以外の面でのデータ活用で対抗するチームは確実に増えている。近い将来、社会人野球や大学野球と同様に、高校野球でも多くのチームが『アナリスト』という肩書を持った部員を抱える可能性も高いだろう。
そしてもう一つ大きい要因としては延長10回からタイブレーク制(無死一・二塁からスタート)が導入されたことではないだろうか。この夏も明徳義塾、関東一、二松学舎大付などの強豪が延長タイブレークの末に敗退している。力の劣る相手はヒットを続けて打つことは難しくても、タイブレークとなれば最初から2人の走者が出塁した状態から攻撃することができ、攻撃力の差は小さくなると考えられる。終盤まで同点という展開であれば何とかタイブレークに持ち込み、そこに勝機を見出すというケースも今後は増えていくのではないだろうか。
高校野球全体の流れとしては少子化や部員の減少によって、力のある選手は一部の強豪校に集まり、甲子園で上位進出する学校は寡占化が進んでいるように感じられる。ただ、これまでに述べた情報量の増加やタイブレークの導入によって、これまでと違う戦い方に活路を見出すチームが出てくることも考えられる。今後、これまでとは違うやり方で本当の意味での“波乱”を起こすチームが増えることにも期待したい。(文・西尾典文)
●プロフィール
西尾典文 1979年生まれ。愛知県出身。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行っている。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所(PABBlab)」主任研究員。