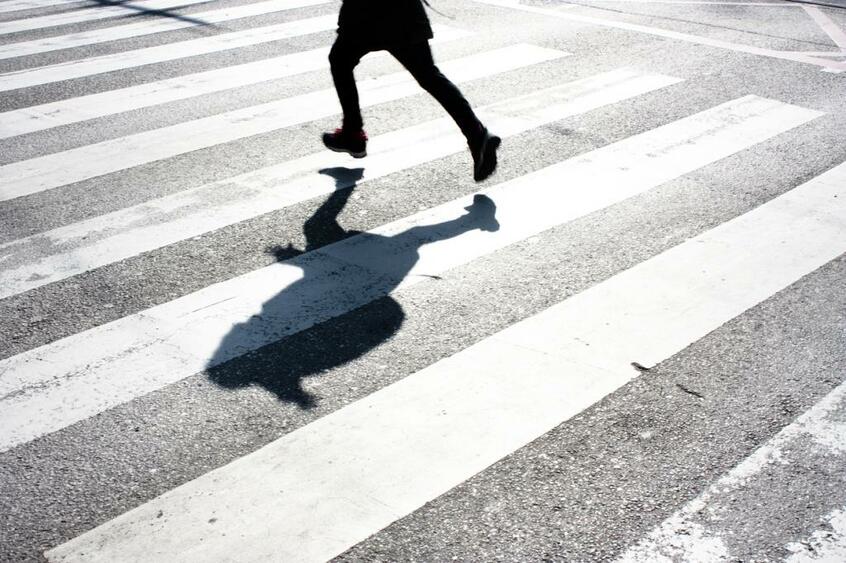
いよいよ2学期が始まり、親が子どもたちの世話から解放される時期だ。ホッとする一方で、登下校に加えて新しい塾や習い事がスタートするなど、子どものひとり行動が増える時期でもある。子どもを狙った犯罪のニュース報道は後を絶たず、親の不安は募るばかりだ。地域安全マップの生みの親であり、「犯罪機会論」を専門とする立正大学の小宮信夫教授に、子どもを犯罪から守る方法を聞いた。
【写真】「子どもの身体を守るために性教育は重要」と訴えるタレントは
* * *
プールの水の中で、子どもが知らないうちにわいせつ被害に遭っていたかもしれない――。そんな可能性を想像したことがあるだろうか。
新型コロナウイルス感染防止のため一昨年や昨年は閉鎖されていたプールも、この夏は開放された。この夏休み、家族でプール施設に遊びに行った人も多いだろう。
人が多ければ、犯罪も発生しやすい。
レジャーシートに置いた荷物や財布が盗難に遭わないようにするなどはもちろんのこと、子どもが水着に着替える際は「不審者」に盗撮などされないよう、気をつけるのは親の役目だ。
しかし、だ。
気づかぬ間に「子どもが犯罪の被害者になっているかもしれない」と言うのは、「犯罪機会論」を専門とする立正大学の小宮信夫教授だ。
「特に、プールの水の中は、親からは見えにくい。偶然に手が触れたふうを装い、子どものお尻などを触る痴漢が存在します」
■犯罪者は子ども向けイベントを狙う
恐ろしいのは、こうした子ども向けの施設やイベントには犯罪者が集まりやすいということ。小宮教授が続ける。
「理由は簡単です。確実に、たくさんのターゲット(=子ども)が来るので、犯行のチャンスが広がっているからです」
よくニュースなどで耳にするのは、スマホや特殊カメラなどが使われる、プールや温泉の更衣室で着替える際に起こる盗撮行為。
「しかし、怖いのは水中で触る手口。夢中になって遊んでいる子どもは、触られたと気づきにくい。だから、被害が届けられることはほぼない。わいせつな犯罪行為が起きていると認識されないのです」




































