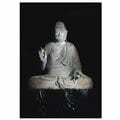四天王像は、仏像が住むという世界、須弥山中腹の東西南北を守護するとされる。それがお寺の本尊を守護する仏像として、本尊の周囲に安置される理由だ。特徴は、足下で邪鬼を踏み、それぞれ手には鉾や戟を持って威嚇している姿だ。この中で、北方を守護する多聞天像は、戦功に威力を発揮する仏像として単独で信仰されるようになり、その際、名称が毘沙門天となった。 お寺の山門には、左右に2体、正面を威嚇する天が安置される。仁王像である。2体の仁王像は、通常は向かって右に口を開けた阿形、左に口を閉じた吽形が配置される。仁王像は、金剛杵という武器を持っているので金剛力士とも称される。本来仁王像は、インドでは1体で制作されており、中国で左右2体となった。1体で表現された像は、執金剛神といわれる。
阿修羅は、もとは破壊の神、悪神とされてきた。しかし仏教に取り入れられ、その威力で仏教の世界を守護する天となる。ちなみにアは非、シュラは天、つまり天に非ずという意味がある。仏法を守護する八部衆の1体となり、釈迦の説法を聴く聴衆としても登場する。
日本では、女性の姿で表現される弁才天と吉祥天も人気を得た天である。弁才天は、奈良時代には多臂の像で制作されるが、次第に二臂となり学問芸術の天ということから琵琶を持つ姿になっていく。また室町時代に成立したという七福神に組み込まれ、広く人々に信仰された。吉祥天は、ヒンドゥー教ではビシュヌ神の妃であり、仏教に取り入れられてから毘沙門天の妃とされるようになる。
その他、薬師如来の眷属・十二神将、大黒天も天に属する。大黒天は、インドのシバ神の化身マハカーラ神で破壊と戦闘の神であった。そのため本来は忿怒の表情だったが、日本では「だいこく」と読むため、伝統的な神・大国主命と習合し、穏やかな表情になった。
※週刊朝日ムック『歴史道 Vol. 23 仏像と古寺を愉しむ』から