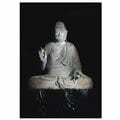五大明王は通常、不動明王を中心に東に降三世明王、南に軍荼利明王、西に大威徳明王、北に金剛夜叉明王が安置されている。それぞれ多面、多臂の像で動きのある姿となっており、三目や五目など多眼で表されることもあるので、見る者を圧倒させる。愛染明王は、煩悩即菩提(愛欲や執着を悟りに変える)という密教的な考えを具現化した仏像である。調伏の仏像とも、あらゆる願い事を叶えてくれる仏像ともいわれる。髪は逆立ち、髪の間に獅子を載せる。左右3本計6本の腕をもち、手には弓、矢、蓮華を持つが、左腕に1本だけ何も持たない手がある。これは願い事によって持つものを変えるからといわれている。孔雀明王は、毒蛇を食べる孔雀を神格化したヒンドゥー教の神を仏教に取り入れて成立した仏像。特徴は明王の中でも忿怒の表情ではなく穏やかな顔で表現されること。孔雀の上に乗り、一面四臂で表現され、手には蓮華、孔雀の羽などを持つ。光背は孔雀の羽根で表される。単独で安置されることが多く、除災、苦難を取り除く仏像として人々に信仰された。
インド古代神話の神々が
仏教の守護神となる
天と称される仏像は、仏教世界の守護神である。天の表現方法は様々で、如来・菩薩・明王以外の表現であれば天と推測することができる。天は、もともと仏教が成立する前にインドに古来あったヒンドゥー教とバラモン教の神を取り入れて成立している。四天王や金剛力士、阿修羅像なども天に属す。
天の中で梵天と帝釈天は、仏教が成立する前のインドで重要な神であった。バラモン教の最高神、万物の根源であるブラフマー神が釈迦の修行中を見守っていたとされ、仏教の成立後に取り入れられ梵天となる。また、古代インドで雷を神格化した戦士の英雄インドラ神が仏教の成立後、帝釈天として守護神となる。どちらも、奈良や京都の古寺では見かける。古代日本の仏教では特に仏法を守護する仏像として重視されていた。