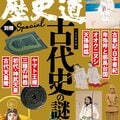なお、元康の初陣は永禄元年(1558)二月、今川氏に敵対する三河の国衆寺部城(愛知県豊田市)の鱸氏(鈴木重辰)攻めで、初陣を勝利で飾っている。元康としては、この初陣の手柄で岡崎城へ戻ることができると考えていたのかもしれないが、岡崎城への復帰はならなかった。岡崎城は今川方の在番衆による支配が続けられていたのである。
一方、酒井忠次、石川数正といった三河武士団の中枢となる家臣が、近侍として元康とともにいた。帰還できなかった岡崎城にも、宿老の鳥居忠吉(元忠の父)がいた。元康の初陣初勝利は、これらの家臣の尽力もあった。
三河の領有をめぐって義元と争っていた織田信秀が天文二十一年(1552)三月三日没した。跡を継いだのが信長である。信長が「大うつけ」などといわれていたことは周知の通りである。義元はそのころ、甲斐の武田信玄、相模の北条氏康と「甲相駿三国同盟」を結んでいたので、背後を心配することなく、三河から尾張へ駒を進めることが可能となり、織田家の家督交代期の混乱状況を好機とみて尾張への侵攻を開始。尾張の沓掛城や鳴海城などが今川方となっていた。 そして、いよいよ満を持し、永禄三年(1560)五月十日、義元の先鋒として遠江井伊谷城(浜松市北区)の城主・井伊直盛と三河の松平元康が駿府今川館を出陣していった。二日遅れて五月十二日、義元も自ら2万5000の大軍を率いて出陣していった。
なお、このときの出陣の狙いについて、古くは上洛説が唱えられていた。それは、小瀬甫庵の『信長記』に、「爰(ここ)に今川義元は、天下を切て上り、国家の邪路を正んとて、数万騎を率し、駿河国を打立しより……」などと、書かれていたからである。
しかし、現在は上洛説が否定され、三河確保のためとする説や、鳴海城および大高城が信長方の砦によって封鎖されているのを、解除するためとする説が有力視されている。ただし、このとき、2万5000という今川氏にとっての最大動員兵力であること、義元自身の出馬であったことからみて、尾張をこの際、奪取してしまおうという狙いもあったのではないかと考えられる。
(次回へ続く)
※週刊朝日ムック『歴史道 Vol.25 真説!徳川家康伝』から抜粋
こちらの記事もおすすめ 【記事の前編】徳川家康のルーツ「十八松平」はこうして生まれた 絶えることのなかった一族内争いと「守山崩れ」