
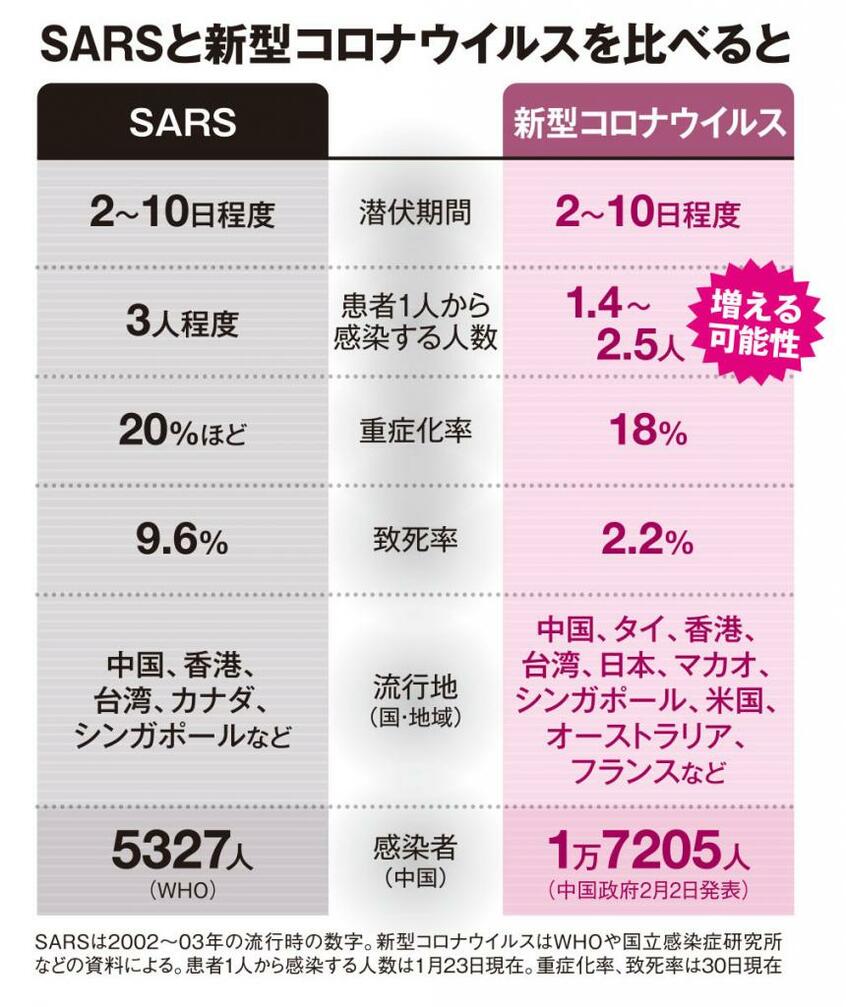
新型コロナウイルスによる肺炎が急速に広がり、WHOが「緊急事態」宣言に踏み切った。 いわれのないデマやヘイトまで流布されるなか、実際にはどこまで恐れるべきなのか。AERA2020年2月10日号はSARSなど感染症と比較し、その脅威を解説する。
* * *
「これ以上の感染拡大阻止のため一致して行動すべき時だ」
世界保健機関(WHO)のテドロス・アダノム事務局長は1月30日、記者会見でこう述べた。この日開かれた緊急委員会でついに、新型コロナウイルス感染による肺炎について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に当たると宣言した。
この宣言が出される以前から、すでに世界中に危機感が蔓延(まんえん)していた。発生源となった中国・武漢市は23日、航空機の運航を停止するなど移動を制限。日本政府は29日から、希望する日本人を退避させている。米国やフランスも同様に、チャーター機を武漢市に派遣した。
テドロス事務局長は、緊急事態を宣言した会見でも「不必要に人やモノの移動を制限する理由はない」と述べた。
だが、こうした慌ただしい動きと並行し、いわれのないデマや中国に対するヘイトが飛び交っている。
「中国のコブラの肉を食べることで新型ウイルスに感染する可能性がある」
「新型ウイルスは食塩水で死ぬ」
これらは、AFP通信が「デマ」だと報じたものだ。
日本国内でも次のようなデマが出回り、厚生労働省関西空港検疫所が否定している。
「関西空港から入国した武漢市の観光客から熱を覚知したが、検査前に逃げた」
逃げた理由はこうだ。
「USJと京都へ遊びに行きたいから」
世界各国に感染が急速に広がるなか、もっともらしいデマが拡散されている。
立正大学心理学部の高橋尚也准教授はこう解説する。
「流言の広がりは、あいまいさと重要性に比例するということが古くから明らかにされています。また、あいまいさの中で、不安が大きな役割を果たしています。新型コロナウイルスは、健康を脅かす可能性があるため重要で、どうコントロールできるかはまだわからないというあいまいさがあります。この状況下では、災害時などと同様に、デマや流言が拡散しやすくなっています」



































