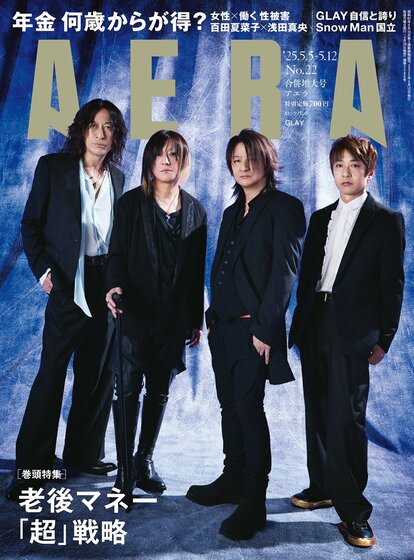「人口が減れば税収も減る。少子高齢化でその影響を最も受けるのが子どもたち。まずは基幹産業の農業で、福島がしっかり稼げるようにする。そこから出た利益を若者の教育にあてるという良い循環をつくるのが最終目標です」(同)
ソーシャルビジネスのあり方は、日本に昔からある「三方よし」という考え方に通じる。社会起業家というと新興企業ばかりが注目されるが、京都産業大学経営学部の大室悦賀(おおむろのぶよし)教授は、
「地域も従業員も環境も大切にして社会課題を『生まない』ようにしてきたサステナブルカンパニーに目を向けるべきです」
と話す。和菓子の虎屋、日本酒の寺田本家、酢の飯尾醸造、「かんてんぱぱ」で有名な伊那食品工業などがそれだ。
伊那食品工業にはトヨタ自動車の豊田章男社長も訪問。経営哲学を学んだという。
大室教授は言う。
「企業が利益目的だけで動いてもエコシステムはつくれない。企業、大学、地域など多様な人たちが関わらないとイノベーションは起こせないんです。つまり、今後のイノベーションのテーマはすべての人に共通の課題の解決。イノベーションとソーシャルイノベーションはほとんど同義になっていくでしょう」
(編集部・竹下郁子)
※AERA 2018年2月5日号より抜粋