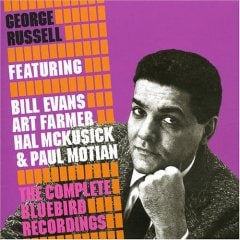

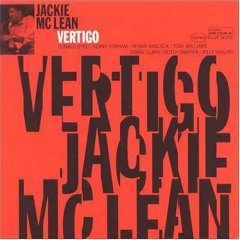
●ビル・エヴァンス(1929‐1980)
パウエル後の最大の改革者
ジャズ・ピアノのアプローチはリズミック(打楽器的)、メロディック(管楽器的)、ハーモニック(鍵盤楽器的)の順に進展した。西洋化の極みとも本家帰りとも思えるハーモニックな改革を成しとげたのがビル・エヴァンスだ。ソロにおいても、エヴァンスはビバップのコード(和音)即応主義から脱し、コードを大まかにとらえ、スケール(音階)にもとづくモード奏法に先駆ける。さらに、ピアノ・トリオの概念をピアニストのワンマン型から三者対等のインタープレイ型に革新した。バド・パウエル後の最大の改革者だ。
ニュージャージー州プレインフィールドで生まれた。6歳から7歳にかけて、ヴァイオリン、次いでピアノを始める。12歳のとき、地元で演奏活動に入った。十代の頃の私的録音が1枚にまとめられている。最も古いのは43年(14歳!)の録音だが、“フィンガーズ”という当時の異名を納得させる技巧派だ。オリジナリティは高いが、めりはりのきいた右手、ストライドを脱した左手、ロックド・ハンズ奏法から、ナット・コールがモデルだったことがわかる。45年5月の録音でのブギ・ウギ奏法は流感にかかったようなものだ。
46年9月にカレッジに進む。47年の録音ではリズムと和声がモダンになっている。前者はビバップの影響、後者は学業の成果だと思うが、やはりコールが支配的だ。8月のロックド・ハンズ奏法による2曲は、ジョージ・シアリングへの接近を示して興味深い。シアリングが渡米したのは47年の初頭だから、素早い反応といえる。49年4月のソロ録音が重要だ。バラード・メドレー2曲での両手を使った綴れ織り奏法と、低音で徘徊するバピッシュな《ジャスト・ユー、ジャスト・ミー》での語り口は「エヴァンス」を予感させる。
融通性発揮から本領発揮へ
50年5月に卒業、ニューヨークで活動するが、51年に徴兵される。54年1月に除隊し、郷里で活動、55年7月に再びニューヨークに出た。50年から53年まで録音はないが、この間にパウエルや、エヴァンスも認めるレニー・トリスターノ派からの影響と離脱があったと見られる。54年に始まる公式録音に両者の影は希薄なのだ。一方で、個性全開というわけでもないが、すべてを過渡期のせいにしてはならない。日銭を稼がなければならなかったエヴァンスの、融通性の産物でもある。実態は、完成しつつあったと見ていいだろう。
完成を促したのは作編曲家で理論家のジョージ・ラッセルにちがいない。56年3月の録音での凶暴なトリスターノにも映る熾烈なソロは、ラッセルが提唱したモード理論に感化されたものだろう。6月のトニー・スコット(クラリネット)の《エオリアン・ドリンキング・ソング》でも、ほぼ「エヴァンス」の域にある。ところが、9月の初リーダー作では本領を発揮していない。概ね、黒人風の粘るタッチと並みのスタイルで通している。レーベル側の戦略と好み(注)だろう。ただし、ソロ録音で見せる抒情はエヴァンス印だ。
57年の夏、微妙な変化が現れる。硬質なタッチと嗜虐的な姿勢が軟化するのだ。チタンからハガネに変わったほどのことだが、これで俄然エヴァンスらしくなる。58年1月のエディ・コスタ(ヴァイブ)のセッションで、ようやくエヴァンスは完成した姿を披露する機会に恵まれた。マイルス・デイヴィス・グループに参加する3カ月前、リーダー作『エヴリバディ・ディグズ』で本領を発揮する11カ月前、スコット・ラファロ(ベース)、ポール・モチアン(ドラムス)とピアノ・トリオの概念を革新する1年11カ月前のことだ。
影響を免れた後進は少ないだろう。エヴァンス派と目された第一陣は、ドン・フリードマン、クレア・フィッシャー、スティーヴ・キューンだ。ハービー・ハンコックはエヴァンスをもとに60年代を代表するスタイリストになった。先輩格では、エヴァンスが一時期モデルにしたシアリング、後期のハンプトン・ホーズがいる。70年代以降も、リッチー・バイラーク、ミシェル・ペトルチアーニ、エンリコ・ピエラヌンツィなどの傑物が出た。
注:プロデューサーのオリン・キープニューズは、もとはアーリー・ジャズの研究家で、黒人志向だった。この時点で、エヴァンスの新しさを理解していたのだろうか。同作のソロ録音の2日後とトリオ録音の前日には、ケニー・ドリューのトリオ録音に臨んでいる。
●マッコイ・タイナー(1938‐)
60年代のスタイリスト第1号
マッコイ・タイナーの快進撃が止まってから30年ほどたっている。多くのファンにとって、もはやマッコイはジョン・コルトレーン(テナー)の破竹の進撃をささえた(だけの)「博物館級の人」なのかもしれない。しかし、マッコイが編み出した左手の4度重ねのヴォイシングと右手のペンタトニック(5音音階)・フレーズは実に斬新だった。マッコイはモード奏法の一つの在り方を示し、絶大な影響をおよぼす。エヴァンスとハービーの間にあって、60年代のピアノ・スタイルの方向を示した功績は改めて評価すべきだろう。
フィラデルフィアで生まれた。13歳でピアノを始め、15歳の頃にはジャム・セッションに興じるようになる。仲間にリー・モーガン(トランペット)やアーチー・シェップ(テナー)がいた。同じ頃、近所に移り住んだパウエルから影響を、弟のリッチー・パウエル(ピアノ)から指導をうける。“バド・モンク”と呼ばれたように、セロニアス・モンクもアイドルだった。高校卒業後、生地で音楽学校に通うかたわら演奏活動を続ける。そんななか、55年に当地を訪れたコルトレーンと知り合い、来訪の度に共演を重ねていった。
59年にアート・ファーマー=ベニー・ゴルソン・ジャズテットに迎えられニューヨークに出る。初録音は59年12月、同僚カーティス・フラー(トロンボーン)のセッションで、60年2月のジャズテットのセッションがこれに続く。「節」「弾み」「ブルース」のないレッド・ガーランド~ウィントン・ケリーといったところで、コルトレーンがどこに魅かれたのか謎を残す。6月にコルトレーン・カルテットに加わる。同月のフラー、フレディ・ハバード(トランペット)のセッションでもハードバップ・スタイルに変わりはない。
ジャズ史上空前の特急仕上げ
同年9月、コルトレーン・カルテットでの初録音に臨む。マッコイの激変ぶりに唖然とせざるをえない。こじんまりとし弱さは残るが、前述した独創的なスタイルをほぼ手中におさめているのだ。これほど斬新なスタイルを3カ月足らずで編み出せるものなのだろうか。コルトレーンやエルヴィン・ジョーンズ(ドラムス)と研鑽を重ねるなかで築きあげていったと見るしかなさそうだ。パウエル以来の右手偏重主義から脱した、両手によるダイナミックなスタイルは、早くも10月のコルトレーンの連続セッションで完成している。
しかしそれは、しばらくはコルトレーン御用達だった。自分のスタイルだという意識や全面的に打って出る自信がなかったのか、初期のリーダー作とコルトレーン以外のセッションでは、以前に通じる端正なスタイルでほぼ通している。ときには暑苦しく思える疾風怒濤スタイルに徹するのは64年からだ。いかなる心境の変化があったのか、またしても謎を残す。マッコイの直系にはジョン・ヒックス、ジョー・ボナーがいる。あとはエヴァンスやハービーとの融合系で、チック・コリア、バイラーク、ピエラヌンツィが代表格だ。
●ハービー・ハンコック(1940‐)
60年代のスタイリスト第2号
団塊あたりの世代にとって、ハービー・ハンコックこそ、ほぼリアル・タイムで聴いてきたミュージシャンではないだろうか。ジャズを聴き始めた頃は、ジャズ喫茶でハービーの参加作がかからない日はなかった。個人的には、ファンク路線に邁進した頃も大いにお世話になった?ものだ。そんなわけで、最も親しみを感じるし、何をしようとも好意的に見ていられる。舞台からご高説をたれることをのぞいてはですが。ハービーがマッコイと並んで60年代を代表するスタイリストであることを悟るのは、かなりあとのことだった。
シカゴで音楽一家に生まれた。7歳でピアノを始め、11歳のときには交響楽団と共演している。中学に進むと、クラシックに励む一方でR&Bに熱中した。印象派~現代音楽の素養とファンク、ハービーの要素の芽生えだ。高校時代にジャズに目覚め、シアリングなど白人ピアニストを研究し、バンドを組む。アイオワのカレッジに進み電子工学を専攻するが、のちに芸術学部に転部する。60年6月に卒業、シカゴで演奏活動に入った。12月にドナルド・バード(トランペット)と共演、気に入られ61年1月にニューヨークに出る。
モード奏法とアウト感覚の開花
初録音は60年末か61年初め、バードのセッションだ。マッコイの初録音に比べて安定している。左手はエヴァンスで右手はガーランド~ケリー、新旧同居とも白黒同居ともいえるスタイルだ。続くバードの諸作や62年5月の初リーダー作ほかでは、次第にエヴァンス色を強めていく。ほぼ出来あがった姿は63年1月のバードの『ア・ニュー・パースペクティヴ』、2月のジャッキー・マクリーン(アルト)の『ヴァーティゴ』にとらえられている。ケリー風も残るが、後者でのモーダルで戦闘的なアプローチはハービーそのものだ。
完全版ハービーには何かが足りない。アウト感覚、つまりフリーなアプローチだ。3月のリーダー作『マイ・ポイント・オブ・ヴュー』にはある。一月ほどの間に何があったのか。同作の9日前にエリック・ドルフィー(アルト)と共演している。大した演奏は残していないが、このときにドルフィーに感化され、アウト感覚をものにしたと見るしかない。4月にマイルス・グループに参加し、奏法の総仕上げに向かう。8月のリーダー作『インヴェンションズ&ディメンションズ』に聴くハービーは、すっかり出来あがっている。
このあとはマイルス・グループにあって、アウト感覚とモード奏法に磨きをかけていく。前者にはトニー・ウィリアムス(ドラムス)が、後者にはウェイン・ショーター(テナー)が大きく寄与した。影響をうけた者に、近い世代ではミッキー・タッカー、ジョージ・ケイブルス、より若い世代ではバイラーク、うんと若い世代ではケニー・カークランドがいる。プロ、アマを問わず、影響をうけた者の数はマッコイのそれを上まわるようだ。
ピアノは今回でおしまいにし、次回はギターに入らせていただく。
●参考音源(抜粋)
[Bill Evans]
Very Early/Bill Evans (43-49 E3)
The Complete Bluebird Recordings/George Russell (56.3-12 Lone Hill)
New Jazz Conceptions/Bill Evans (56.9 Riverside)
Guys and Dolls Like Vibes/Eddie Costa (58.1 Coral)
[McCoy Tyner]
Imagination/Curtis Fuller (59.12 Savoy)
Meet The Jazztet/Art Farmer=Benny Golson (60.2 Argo)
Like Sonny/John Coltrane (60.9 Roulette)
My Favorite Things & others/John Coltrane (60.10 Atlantic)
[Herbie Hancock]
Out of This World/Donald Byrd=Pepper Adams (60/61 Fresh Sound)
Vertigo/Jackie McLean (63.2 Blue Note)
Miles Davis in Europe (63.7 SME)
Inventions and Dimensions/Herbie Hancock (63.8 Blue Note)


































