
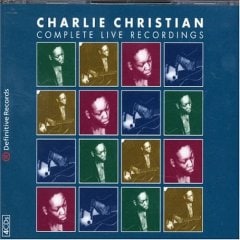
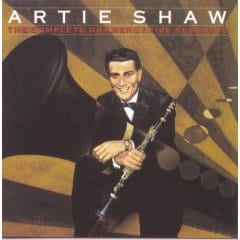
●ジャズ・ギター前史
バンジョーからギターへ
ジャズ創成期から40年あまり(アコースティック・)ギターは恵まれない楽器だった。一にも二にも音量が乏しかったせいだ。30年代の終わりにエレクトリック・ギターが導入されて音量と表現力が増すまで、日陰の身に甘んずるほかなかった。リズムおよびコード楽器の役割は、長らく強力なサウンドが出せるバンジョーが担う。そのバンジョーにしても、メロディー楽器への移行は果たせなかった。経験上、バンジョー(注)は弦の張りが強く、弦高が高く、音域が狭く、シングル・トーンによるソロには不向きだったと思う。
バンジョーでソロをとった者がいなかったわけではない。先駆者に、キング・オリヴァー(コルネット)、ルイ・アームストロング(トランペット)、ジェリー・ロール・モートン(ピアノ)の20年代の名演にもれなく参加した、ギターも弾くジョニー・センシア(1890‐1966)がいる。ただし、多くはコード・ソロで、シングル・トーンによるソロもアルペジオに類するものだ。リズムの名手と見るべきだろう。大方のバンジョー奏者は律儀にフォー・ビートを刻み、たまにフィルイン(装飾音)をカキ鳴らす程度のことだった。
30年代に入ると、ニューオリンズ伝来のリズム楽器だったチューバはベースに、バンジョーはギターに置き換えられていく。サウンドの洗練化にともなうもので、マイクロフォンの進歩がそれを後押ししたということだろう。しかし、ギターそのものの音量と表現力が増したわけではないから、地位が劇的に向上することはなかった。バンジョーから地位を譲られたとはいうものの、ギターに持ち替えた奏者は相変わらず律儀にフォー・ビートを刻み続け、まれにソロをとる場合でも、バンジョー譲りのコード・ソロで通していく。
ジャズ・ギターの開拓者
その数年前、ギターはソロ楽器として歩み始めてもいた。先鞭をつけたのは、アーバン・ブルースの名手、ロニー・ジョンソン(1899‐1970)だ。ルイの録音(27年と29年)やデューク・エリントン楽団の録音(28年)を通じて、ロニーはシングル・トーンによるギター・ソロをジャズ界に移植する。影響された大物に、ロニーとは何度も共演したエディ・ラング(1902‐1933)と、テディ・バン(1909‐1978)がいる。彼らは、リズムおよびコード楽器にすぎなかったジャズ・ギターに、メロディー楽器の機能を加えた開拓者だ。
ラングは知的で洗練され、白人ながら優れたブルース感覚をそなえた名手だった。超売れっ子の最中、扁桃腺の手術がもとで夭逝する。ギターの地位が低かったこととラングのレベルが段違いだったことから、直接的な影響力はジャンゴ・ラインハルトやエリントン楽団のフレッド・ガイあたりにとどまった。ただ、趣味のよいライン、繊細なコード・ワーク、洗練されたブルース感覚は白人ギタリストに脈々と受け継がれていったように思う。バリー・ガルブレイス、ジム・ホール、ビル・フリゼールなどに、それを強く感じる。
バンはブルージーでハード・ドライヴィング、群を抜くスウィング・ギタリストだった。センシアの影響もうけている。ラングとバンがソロ楽器の地位に導いたにもかかわらず、ギターはブレイクしなかった。無理もない。ベニー・グッドマン(クラリネット)ですら、チャーリー・クリスチャンのオーディションをもちこまれたときに、「誰がギターなんて聴きたいんだ?」と反発した時代なのだ。ジャズ・ギターに革命がおきるには、エレクトリック・ギターを抱えたクリスチャンが、表舞台に登場するのを待つしかなかった。
注:一般的にアーリー・ジャズで使うテナー・バンジョーは4弦で、カントリー・ミュージックで使う5弦バンジョーより音域は高く狭く、金属的なカン高いサウンドを発する。
●チャーリー・クリスチャン(1916‐1942)
田舎の天才、都にのぼる
チャーリー・クリスチャンの功績は、エレクトリック・ギターによりギターを管楽器と対抗しうるソロ楽器の地位につけ、後進に絶大な影響をおよぼし、オフ・ビート感覚と斬新なコード進行でビ・バップの方法論を示唆した、ということになるだろう。エレクトリック・ギターを使った先駆者ではないし、シングル・トーンによるソロをとった先駆者でもない。しかし、先人とは次元が異なった。ギターをソロ楽器として確立したのはクリスチャンにほかならず、ジャズ・ギターの歴史はここに始まったといっても過言ではない。
テキサス州バナムで音楽一家に生まれる。2人の兄もクリスチャンも幼少期に父から弦楽器を仕こまれた。やがて一家はオクラホマ・シティに移る。26年に父が死去、ギターを受け継いだがサイズが合わず、ウクレレを演奏していた。32年に高校を中退、ギタリストとしてプロ入りする。同年、レスター・ヤング(テナー)と知り合い、ジャムを重ねた。34年にはトリオを率い、37年にはエレクトリック・ギターを手に入れ、ローカル・バンドに加わって中部をツアーする。39年の春にオクラホマ・シティに戻り、コンボを率いた。
7月にメアリー・ルー・ウィリアムス(ピアノ)の口利きでジョン・ハモンド(プロデューサー)に会い、8月16日にグッドマンのオーディションを受けたが、グッドマンの無関心とクリスチャンの緊張から不首尾に終わった。その夜、ダンスホールに出演していたグッドマン楽団の休憩中、ハモンドはクリスチャンを忍びこませる。ステージに戻ったグッドマンは不快感も露わに曲名を告げたが、演奏は47分も続いた。結果、当代随一の人気バンドにクリスチャンは雇われ、田舎の天才は瞬く間に全国区のスターにのぼりつめる。
ジャズ・ギターの革命児
表舞台に登場した時点で、クリスチャンは出来あがっていた。それ以前の録音はない。残された録音に先人の痕跡は認められるだろうか。素朴でいて都会的なブルース感覚はロニー・ジョンソン譲りだろう。アコースティック・ギターを弾いたエドモンド・ホール(クラリネット)の録音が好例だ。クリスチャンより先にエレクトリック・ギターを弾いたエディ・ダーハムの影は、クリスチャンが唯一コード・ソロをとった《スターダスト》にうかがえる。30年代の半ばにジャンゴ風のソロをとったという話は、後知恵ではないか。
クリスチャンは終生レスターをアイドルとした。スロー・テンポの寛いだ演奏で、まれにレスターのフレーズが顔を出す。それは41年3月のジャム・セッションで聴くことができる。ほかでは、さほど近似性は感じられない。クリスチャンはスタッカート感が強く、乗りもイーヴン、キチンとしている。レスターはレガート感が強く、小節線は無視するし、どこかルーズだ。共通するのはホリゾンタルなアプローチしかないと思う。このほか、ウエスタン・スウィング・ギターの影響もありそうだが、またの課題にさせていただく。
クリスチャンの革新的な奏法は無数の追随者を生んだ。例外はジャンゴくらいではないか。クリスチャン後の主だったギタリストを列挙するだけで紙幅はつきる。それで終わらせたい誘惑を抑えて、自身も大きな影響源となった、各年代を代表するギタリストをあげておこう。50年代はバーニー・ケッセル、ジミー・レイニー、タル・ファーロー、60年代はジム・ホール、ウェス・モンゴメリー、70年代はジョージ・ベンソンだ。このほか、ほとんどのジャズ・ギタリストがクリスチャンのDNAを受け継いでいるといえるだろう。
●バーニー・ケッセル(1923‐2004)
今一人のオクラホマの天才
クリスチャンはビ・バップの方法論を示唆したが、バッパーではなかった。そうなる前に夭逝してしまったというべきだろう。コード進行の理論化、オフ・ビート・バッキング、コード・ソロといった積み残しの解決は後進にゆだねられた。クリスチャンのスタイルに基づき、バップの語法を消化し、いち早くモダンなスタイルを完成させたのがバーニー・ケッセルだ。闊達なシングル・トーンによるソロと華麗なコード・ワークを組み合わせ、ダイナミックなスタイルを築いた。モダン・ジャズ・ギター史の1頁目にくる巨人だ。
オクラホマ州マスコギーに生まれた。12歳でギターを手にし、14歳のときに黒人バンドで演奏を始める。当地で唯一の白人ミュージシャンだった。黒人と誤認しかねないファンキーな感覚は、ここで培われたのだろう。16歳のとき、オクラホマ大学のバンドに加わって演奏していた会場に、既にスターになっていたクリスチャンが訪れ、運命的な出会いを果たす。これでプロになる決意を固め、42年にハリウッドに出た。ほどなくチコ・マルクス楽団に雇われ、入退団を繰り返したあと、43年にロスに定住し、ラジオの仕事に就く。
そのあとケッセルが参加したとされる録音(注)は入手できなかった。ただ、時期と場所からいって、レス・ブラウン楽団への参加は疑わしい。ケッセルもオーディションに落ちたと語っている。参加が事実でも、当時のビッグ・バンドでソロは許されていないだろう。公式初録音は44年8月、チャーリー・バーネット楽団の録音だが、ソロはとっていない。初期のケッセルが聴ける録音で入手し易いのは、同月に出演した映画『ジャミン・ザ・ブルース』のサウンドトラックだ。クリスチャンにそっくりで、なんとも微笑ましい。
クリスチャン+ビ・バップ
直後にアーティ・ショウ楽団に招かれ、45年の暮れまで在団する。ビッグ・バンドによる録音に出番はあまりない。重要なのは、選抜メンバーによるコンボ、グラマシー・ファイヴの録音だ。45年1月の録音ではソリッドでグルーヴィーな個性を打ち出し、7月の録音ではバップの語法をとり入れ、モダン・クリスチャンというべきスタイルになっている。ツアーを続けるなか、最先端の音楽に触れたのだろう。バップ旋風が巻き起こる以前のロスにとどまっていたら、ビ・バップの洗礼をうけるのは少し先になったかもしれない。
出来あがりつつある姿は46年1月のチャーリー・ヴェンチュラ(テナー)の録音に、出来あがった姿は47年2月のチャーリー・パーカー(アルト)の録音にとらえられている。8月のライオネル・ハンプトン(ヴァイブ)のライヴ録音では「未だクリスチャンの幻影を強く感じる」という方があるが、スウィング系のお膳立てに合わせたにすぎまい。また、51年から53年まで在籍したオスカー・ピーターソン・トリオでスタイルを完成させたという方もあるが、ようやく才能を開花させる場を得たのだと見る。ケッセルの影響が色濃いのはハワード・ロバーツだ。初期のレイニー、ホール、ウェスにも痕跡が認められる。
注:レス・ブラウン楽団の17曲(43年3月、8月、11月、44年5月)、ティミー・ロジャース・コンボの1曲(43年12月)、ジャック・マクヴィー・コンボの1曲(44年4月)。
●参考音源(抜粋)
[The Prehistory of the Jazz Guitar]
Johnny St.Cyr: The Complete Hot Five and Hot Seven Recordings/Louis Armstrong (25.11-27.12 SME)
Lonnie Johnson: The Okeh Ellington/Duke Ellington (28.10 & 11 SME)
Eddie Lang: Jazz Guitar Virtuoso/Eddie Lang (27.4-32.2 Yazoo)
Teddy Bunn: Big Soul Clarinets/Johnny Dodds & Jimmie Noone (37.12 & 38.1 MCA)
[Charlie Christian]
Complete Live Recordings/Charlie Christian (39.8-41.6 Definitive)
The Genius of the Electric Guitar/Charlie Christian (39.10-41.3 SME)
[Barney Kessel]
The Complete Gramercy Five Sessions/Artie Shaw (45.1-8 Bluebird)
Charlie Ventura 1945-1946 (46.1 & 3 Classics)
Charlie Parker Story on Dial Vol.1 (47.2 Dial)


































