
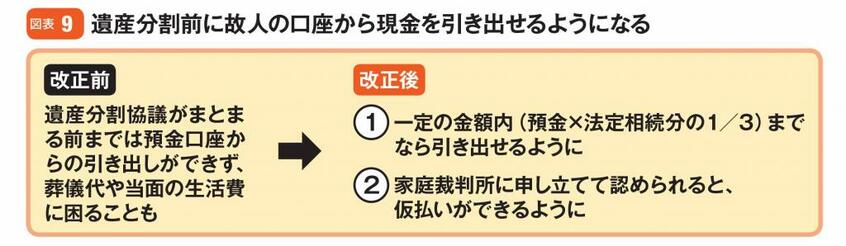
約40年ぶりに大きく変わった相続制度が、2019年1月以降、順次施行される。配偶者の権利が擁護されると、期待の声も大きいが、聞こえのいい言葉だけを拾って喜んでいると、家族間の火種も増えるという。週刊朝日ムック『定年後からのお金と住まい2019』より、相続改正の大切なポイントをお届けする。
* * *
夫が2千万円の自宅と2千万円の現金を残して亡くなり、妻と子ども2人が相続するケースで見てみよう。改正前は、住み慣れた家を相続するだけで妻の法定相続分の「2分の1」はいっぱいになってしまい、預貯金等の現金は相続ができなかった。
だが、改正後は、妻は「配偶者居住権」を設定することで、他の相続人である子どもは「負担付き所有権」の取得が可能になる。結果、妻は1千万円の「配偶者居住権」と1千万円の現金を相続でき、家も生活資金も確保できるようになった。一方の子どもたちは500万円の「負担付き所有権」と500万円の現金を相続することになる。
■安易の「配偶者居住権」を設定するのはNG?
そもそも、モメずに遺産分割協議のテーブルについて円満に結論を出すことができれば「配偶者居住権」など設定しなくてもいい。
このケースでも、「母さんは、自宅の所有権だけだと不安だろうから現金1千万円も相続しなよ。僕たちは500万円ずつでいい」と子どもたちの合意があればそれで解決だ。または、相続税の問題や登記等の手続きの煩わしさから、「自宅の所有権は長男の僕がもち、母さんが住み続ける。預貯金は母さんと妹で1千万円ずつ分けるのはどうかな」と提案ができ、相続人全員が合意するなら解決だ。
その合意ができないからモメる。そんな家庭で「配偶者居住権」が創設され「居住権」と「所有権」に分けてしまったら、どうなるだろう。再び不動産をめぐってモメてしまう原因になることは想像に難くない。さらに、これが実子ではなく、「前妻の子と後妻」などのケースだと、さらに事態がこじれることも予測される。安易に「配偶者居住権」を設定するのは、気をつけたほうがいいだろう。
■外国では当たり前!? 「居住権」の設定
ただ、この自宅の不動産を「居住権」と「所有権」に分けることは、その家の財産を守ることになる、という考え方もある。たとえば、改正前に夫(被相続人)の死後、妻が自宅の所有権を相続し、その後、再婚したとする。そして、その再婚相手より早く亡くなってしまった場合、妻の初婚時の自宅の所有権は再婚相手に流れてしまうこともある。
だが改正後、妻が居住権、子どもが所有権に分けて相続したとすると、妻が再婚して再婚相手より先に亡くなったとしても、妻の死亡時に居住権は消滅。所有権のある子どもに自宅は受け継がれ、妻の再婚相手には流れない。『磯野家の相続』の著書があり相続に詳しい弁護士の長谷川裕雅氏はいう。





































