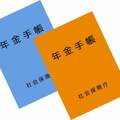「すごい進歩です。母はもともと前向きなので、『なっちゃったものは仕方ない』って言いながらも、がんばっているんです」
Aさんは自宅でも、スタッフから指導を受けた自主トレーニングを欠かさない。しかも、その様子や成果を手紙に記して、外来リハに来たときにスタッフに渡している。もちろん、手紙も左手で書いたものだ。
「本当にここのスタッフが好きで、週1回のこの日が来るのを楽しみにしています。そんな母を見ていると思うんです。生きている(使える)側のほうができない側を補うことって、本当にできるんだって」(息子)
病気やケガ、先天的な要因などで失われ、低下したからだの機能を補ったり、維持したりするために必要なリハビリ。その歴史は意外と浅く、「医学の領域として確立したのは、戦後になってから」と、昭和大学医学部(東京都品川区)リハビリテーション科教授の水間正澄医師は話す。
とはいえ、リハビリも日々、新たな有用性が認められ、進化している。
「以前は、残った機能を活用して能力を高めていくことが、リハビリの主たる考え方でしたが、今は、脳卒中で起こったまひはリハビリで改善できる可能性があることがわかっています。開始時期も以前より格段に早まり、さまざまなやり方が登場しています」(水間医師)
重症度やその人の年齢、体力、持病などの要因でも変わるが、在宅復帰や社会復帰する割合も向上しているという。
※週刊朝日 2014年8月8日号より抜粋