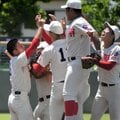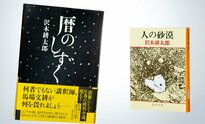歴史的な物価高騰が続いている。自動車が生活に欠かせない人たちにとって、ガソリン代の値上がりは家計の大きな負担になっている。いつまで続くのか。AERA 2023年2月20日号の記事を紹介する。
* * *
交通網が発達している大都市圏はともかく、地方にとって自動車は生活の必需品。ガソリン価格の高騰は家計に大きな痛手で、香川県在住の20代女性はこんなコメントを寄せてくれた。
自動車で通勤しているので、ガソリン代は食費とともに削るのが難しい出費です。ガソリンを極力減らしたくないので、プライベートではほとんど外出しなくなりました。まるで、コロナ禍の“巣ごもり生活”が復活してしまったような状況です。
政府は昨年1月から「激変緩和措置」として、石油元売り会社に補助金を支給している。当初、その上限額は1リットル当たり5円だったが、ウクライナ侵攻に伴う原油価格の高騰を踏まえて、昨年3月に25円、昨年4月に35円に引き上げた。
本来なら、原油価格がピークをつけた昨年6月に、レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均価格は216円弱に達していたはずだった。だが、補助金によって175円弱に抑えられ、その後も実勢価格の推移に応じて13.6~41.1円の抑制が行われてきた。
昨年末に2022年度第2次補正予算でも新たに3兆円を計上し、今年9月末までこの措置が継続することが決まっている。ただし、補助金の上限は1月から毎月2円ずつ減額されていく。
「足元では、補助なしでは185円程度の価格が168円程度に抑えられています。実際の値段が補助の上限額を超えない限りは、今後も168円程度であり続けることになります」
こう指摘するのは、ポスト石油戦略研究所代表でエネルギー研究者の大場紀章さん。ただ、その程度の補助では“焼け石に水”とぼやく読者も少なくない。
コロナ禍前は高くても150円台、コロナショック直後には126円程度まで下がったので、現状の負担は家計にかなり厳しい。(東京都、50代、男性)
また、こんなジレンマを抱えて苦悩している読者も!