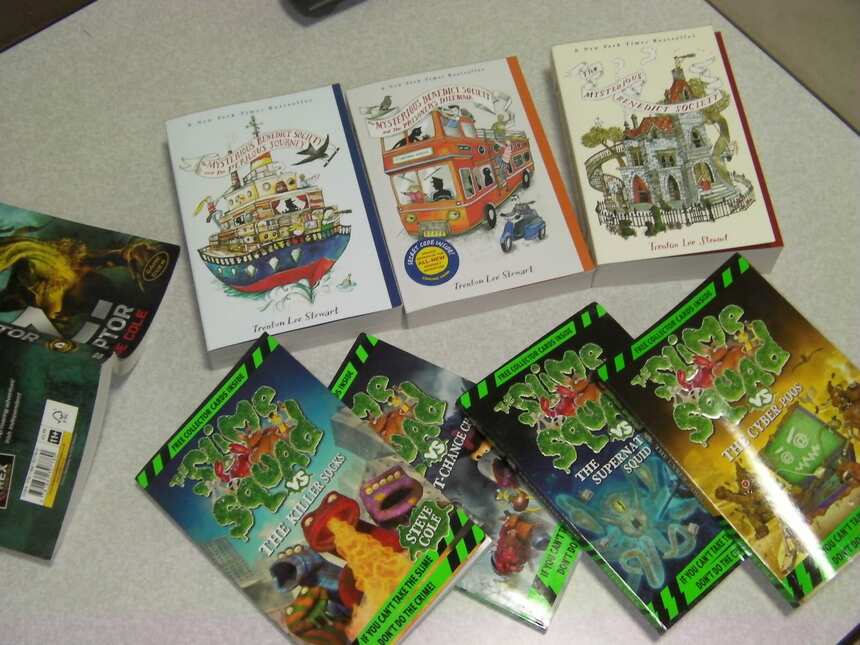――先取り学習と聞くと、ストイックに問題を解き続けているイメージがありますが、タエさんの手法はほんの少しの問題を毎日コツコツ続けること。そのために一番気をつけていたのは、スケジュールを無理に詰め込んだり間違えても怒ったりせず、息子さんがスッと取り組めるタイミングに合わせる配慮だったそう。
タエ:まず覚えたものは忘れるから「一切覚えなくていい」って言ってました。小さいうちに一生懸命やって覚えたって、忘れてしまうのはしかたないじゃないですか。公式だって絶対忘れるから覚える必要はないし、教えることもなかったです。公式を暗記して解くより、考え方やしくみを理解するほうが大事だと考えていました。
キリ:とにかくできなくて怒られるとか、勉強しなきゃいけない、みたいな圧はまったくなかったし、勉強していると思ってなかった。
タエ:性格もあると思いますが、普通に歯磨きしているのと同じような感じで取り組めたのはよかったと思いますね。英語は言葉だから日常にとけ込むんですよ。算数もとけ込ませたかったけど座ってやらないといけないから、英語のようにはできなかったです。もう一つは「どう取り組ませるか」ですね。例えば算数のテキストを買ってくると、ずっと机に置いたままにして息子が座ったら2秒ですぐ始められるよう、文房具を置いてページを開いておいて。帰ってきたらまず風呂に入れて、出てきたらすぐにご飯を食べさせて、取り組むまでのロスをどれだけなくすかを考えてました。算数をやらせるために頑張っていたというより、「算数をやるための時間を作る」ほうに力を注いでたんです。もちろんやりたくない日もあって、そのときはこちらもまた翌日、と思って強制は一切していませんでした。
物理も数学も同じトーンで続けていた
――理数方面の学びに興味を持ってくれたらとせっせと種まきをしてきたタエさん。化学や鉱物の本を渡したこともありましたが、息子さんは興味を持たずに断念。その後、知人の息子さんが国際化学オリンピックの日本代表に選ばれたことで、数学オリンピック以外にも科学系のオリンピックがあることを知りました。調べると物理の国際オリンピックもあり、大会に出場する日本代表選手の選抜を行っている「全国物理コンテスト 物理チャレンジ!」から116枚もの問題をダウンロード。プリントしてキリさんに手渡すと興味を示して解き始め、ここから物理分野の扉が開き始めます。
次のページへ東大推薦入試受験のきっかけは