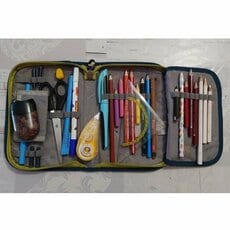父親の育休制度が拡充し、男性育休を取得するパパも増えています。産前産後の父親はどのような悩みを抱えているのでしょうか。信州大学医学部附属病院で育児中の父親の心身の不調を専門にする外来で診察している村上寛医師に聞きました。※前編<“父親の産後うつ”とは? 全国初の専門外来設置から1年、信州大病院医師が語る「父の葛藤」>に続く
【図表】“父親の産後うつ”早期発見チェックポイント4つはこちらパパのメンタルヘルスの不調のサインは?
――いわゆる“父親の産後うつ”はどういう背景で起こるのでしょうか。早期発見のチェックポイントを教えてください。
“父親の産後うつ”という言葉は海外の文献の日本語訳としては適切な言葉ですが、決して適切だと世間に承認された言葉では無いと理解しています。なぜなら母親と父親では産前産後のホルモンの変化や産前産後における役割の違いを踏まえたメンタルヘルス不調に至るまでの過程が異なるからです。“父親の産後うつ”という言葉の使い方は慎重であるべきで、まだまだ議論が必要な言葉です。
一方、父親も産休育休をとると職場から離れて社会的居場所を喪失します。その上で慣れない育児と向き合う。そうなると父親にも心理的身体的負荷がかかり、「なんだか調子がおかしいな」となる。中でもうつ病の既往がある人は再発しやすいです。配偶者の産後直後から産後3、4カ月くらいで受診する人が多いですが、赤ちゃん期以降子どもが活発になる時期に不調になるお父さんもいます。
母親の場合は「赤ちゃんをかわいく思えない」など産後うつを疑うポイントはなんとなく周知されていると思うのですが、父親はそういうサインが分かりづらく、復職してから不調に気づくケースも多いです。ひとつのチェックポイントになるのが育休明けの仕事の状況です。
仕事が好きな人が復職したけど、どうも様子がおかしいという場合は要注意です。育休前と比べると明らかに仕事のケアレスミスが増えた、復職したら仕事への興味が湧かなくなってしまった、という場合はメンタルヘルスの不調が疑われます。私の外来の傾向としては、これが受診のきっかけになっている人が最も多いです。
次のページへ早期発見のチェックポイント