
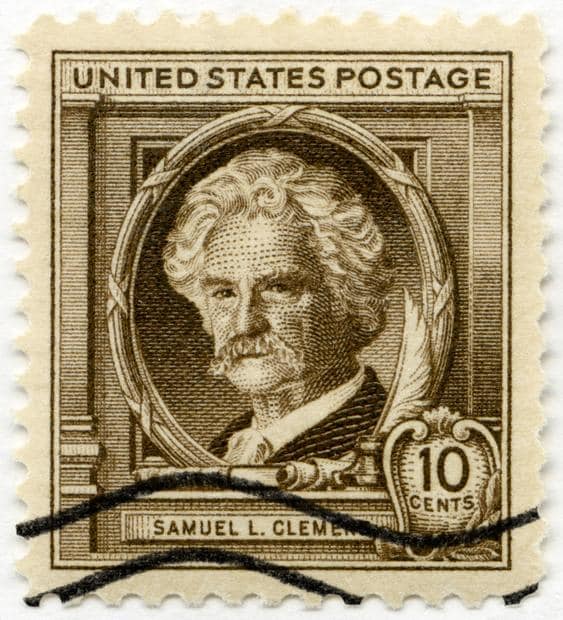
『戦国武将を診る』などの著書をもつ産婦人科医で日本大学医学部病態病理学系微生物学分野教授の早川智医師は、歴史上の偉人たちがどのような病気を抱え、それによってどのように歴史が形づくられたかについて、独自の視点で分析する。今回は作家・マーク・トウェインを「診断」する。
* * *
今年は全国的に梅雨明けが遅い。涼しいのはありがたいが、極めて残念なのは夕空と明け方に長い尾を引くネオワイズ彗星が見えないことである。
海外の友人から、カリフォルニアの砂漠やモン・サンミシェルの修道院、ギリシア神殿を背景にしたネオワイズ彗星の素晴らしい写真を送られるたびに、ため息が出る。日本では沖縄と北海道ではよく見えたようだが、本州、四国、九州は雲間に見えればよい方である。筆者の彗星初体験は中学生時代のウエスト彗星で、その前のコホーテク彗星が空振りだっただけに印象が強かった。1997年のヘールボッブ彗星は東京都心の病院屋上からもよく見えたことを覚えている。
ちなみに、世間では流星と彗星をごっちゃにしている方も多いが、流星は地球の引力に捕らわれた宇宙空間の岩石が大気圏に突入して燃え尽き、せいぜい数秒の成層圏の現象である(燃え尽きないとこの前、習志野に落ちたような隕石となる)。流星の大きなやつを火球というが、普通の流星は毎晩数個から数十個飛んでいる。
毎年8月13日はペルセウス流星群の極大なので、1時間あたり数十個観察できる。彗星はもっと大きな岩や氷の塊で、地球からはずっと離れた軌道を通るので一定の期間は毎晩のように見ることができる。太陽に近づくほど立派な尾を引くが条件がよいとオレンジ色のダストテイルと青いイオンテイルを見分けることもできる。彗星の通った後の軌道には小さな破片が残るので、そこを地球が通るときに流星群が見られるわけである。
彗星には一度太陽に接近すると、放物線軌道でそのまま遠ざかるものと楕円周期的に接近するものがある。周期彗星の中で最も有名なのはハレー彗星だろう。ニュートンと同時代の天文学者エドモンド・ハレーが軌道を計算し、76年毎に見られる大彗星であることが判明した。古くはバビロニアの粘土板から秦始皇帝の年代記や、日本書紀、吾妻鑑などに記録され、有名なのは1066年の回帰でノルマンディー公ギヨームの英国侵攻のタペストリーにも描かれている。前回1986年の接近は北半球では地平に近く、そこそこの光度であったが、南半球では天の川を横切る勇姿が観測された。その前の1910年、前々回の1835年も大変な話題となった。




































