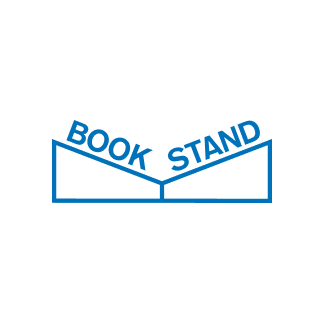BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2016」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは辻村深月著『朝が来る』です。
武蔵小杉のタワーマンションに住む3人の親子----建設会社で働く一家の主・清和と、その妻・佐都子、そして6歳を迎えたひとり息子の朝斗。親子仲睦まじく、夫婦関係も順調な生活を送っていた栗原家に、とある電話がかかってきます。
「子どもを、返してほしいんです」
電話をかけてきた相手の名は、片倉ひかり。朝斗の生みの母です。
夫である清和が無精子症と診断され、苦しい不妊治療を繰り返すも子どもに恵まれなかった栗原夫婦の間に、特別養子縁組によってやってきた、生まれたばかりの赤ちゃん。そのとき、清和と佐都子は共に41歳。
初めて、その赤ちゃんと対面した瞬間の佐都子の心情を、著者は次のように描写します。
「その瞬間、思った。
恋に落ちるように、と聞いた、あの表現とは少し違う。けれど、佐都子ははっきりと思った。
朝が来た、と。
終わりがない、長く暗い夜の底を歩いているような、光のないトンネルを抜けて。永遠に明けないと思っていた夜が、今、明けた。
この子はうちに、朝を運んできた」(本書より)
そして彼らは、待望の赤ちゃんに朝斗と名付けます。小説前半部分では、清和と佐都子が不妊治療を行うにいたるまでの過程、不妊治療の様子、特別養子縁組を受け入れるまでの葛藤が、佐都子の視点から事細かに描かれていきます。
朝斗の育ての親である清和と佐都子。ではいったい、この栗原家に突然電話をかけてきた、朝斗の生みの親である片倉ひかりとは何者なのか。小説後半部分では、ひかりに焦点が当てられ、両親との不和、中学生での妊娠、21歳となった現在にいたるまでの壮絶な半生が描かれていきます。
一本の電話によって繋がった、生みの母と育ての母。しかし、二人はそれ以前に、朝斗を愛しているという点で繋がり続けていました。そして互いに異なる悩みを抱える彼女たちが交錯するとき、そこに何が生まれるのか。特別養子縁組というテーマを通し、血縁や家族の形について、最終的にはある種の希望を仄めかしている作品といえるのではないでしょうか。