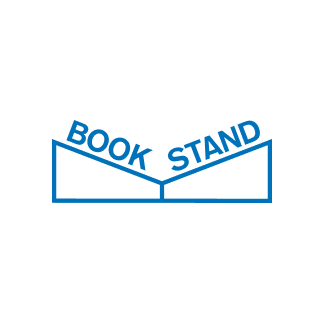イメージについて、「言葉に劣るかもしれないが、言葉を超えうる力をもつ。言葉以下にして、言葉以上。寡黙にして、饒舌。イメージにはたえずそうした対極的な二面性がまとわりついている」と述べる、『イメージの根源へ』の著者・岡田温司さん。
本書では、岡田さんの豊富な知識量と考察力をもって、絵画や音楽、科学といった様々な芸術分野を横断しながら、広くイメージをめぐって生じる問いに向き合っていきます。
「絵画論」「光、色、音」「美学論=感性論」という三部構成からなる本書ですが、その第一部の一つめの論考である「イメージの根源、根源のイメージ」は、次のような言葉ではじまります。
「『絵画とは何か』、あるいはもっと広く『イメージとは何か』というストレートな、しかし困難な問いにアプローチするにあたり、その重要な手掛かりとなるように思われる、西洋の三つの神話がある」
岡田さんは、絵画の起源は「西洋の三つの神話」にあるといいます。その三つの神話とは、「影」と「痕跡」と「水鏡」にかかわる神話。
たとえばそのなかの一つである「影」にかかわる神話は、戦地に赴く恋人の影の輪郭をなぞったことから絵画が生まれたという内容だそうです。
さらにその影の主である、戦地に赴く恋人の兵士には死が待っているかもしれないことから、絵画の根源には人間の愛と死があり、それこそが絵画そしてイメージの永遠のテーマなのだと、岡田さんは指摘します。
「『愛人の肖像』というすばらしい研究書を著わしているイタリアの古典学者、マウリーツィオ・ベッティーニによると、イメージは本来、ギリシア語で『ポトス』、ラテン語で『デシデリウム』と呼ばれる感情、つまり失ったものへの願望や哀惜の念と深く強く結びついている、という」(本書より)
かつて「亡霊」や「幻影」といった含意さえあった「イメージ」という概念。岡田さん自身、イメージへの問いは「人間への、歴史と現代への、共同性への問いと無関係ではありえないのだ」と述べていますが、本書ではまさに古く神話からデジタル化の進む現代までを視野に入れた、読み応えのある一冊となっています。