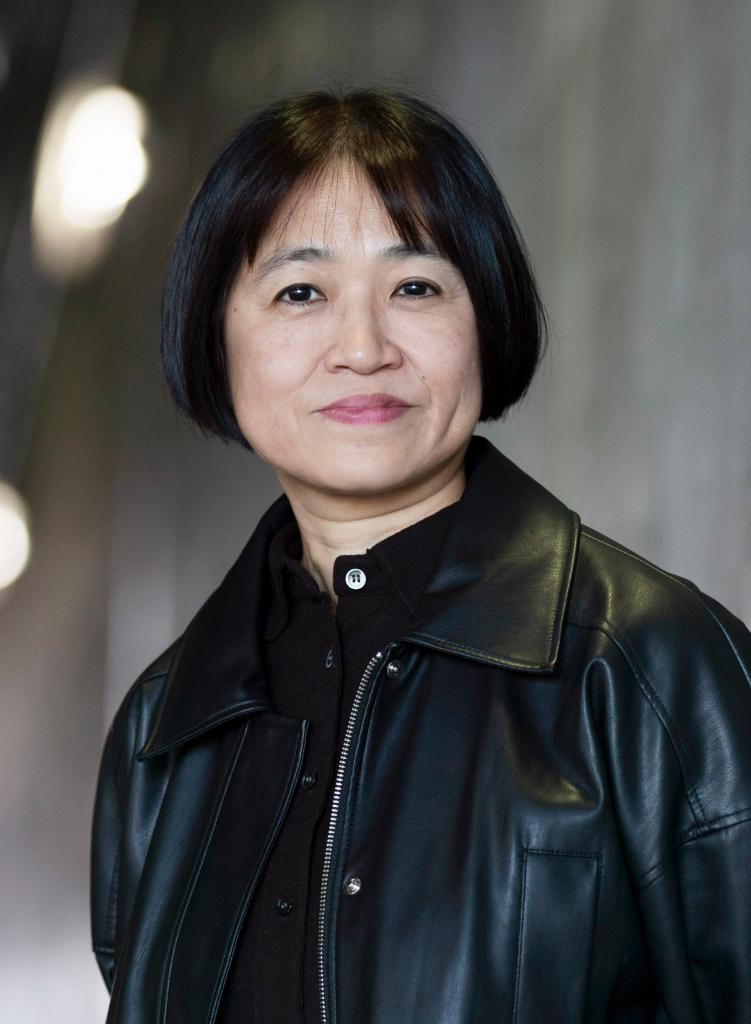
奥多摩の橋から二人の女性が飛び降りて亡くなった。恩田陸さんの新刊『灰の劇場』(河出書房新社、1700円[税抜])は、1994年に起きたこの事件を基にした長編小説だ。
「新聞で見た記事が印象に残っていて、いつか書こうと決めていました」
40代半ばだった二人の女性は私立大学の同級生。大田区のマンションで一緒に暮らしていた。なぜ二人は同居し、なぜ死を選んだのか?
作中には恩田さんを思わせる小説家が登場し、「そろそろあれを書いておかなきゃ」と二人の話に取り掛かる。そして、彼女たちの出会いから死に至るまでが描かれる。
さらにこの物語が舞台化される場面が加わり、三つのパートが入れ替わりながら小説は進んでいく。ノンフィクションに近づいたフィクションだ。
「書いているうちに、こういう形になっていきました。もともと書きながら考えるほうなんですけど、今回は今までにないくらい考えました。自分では新しいことをやっているつもりはなかったんですけど」
事実と創作の境目をどうするか、ノンフィクション風の書き方など、試行錯誤した。恩田さんが現実の事件を題材にするのはこれが初めてだ。今までは自身のテクニックが伴わないとして、取り上げてこなかった。
「もっと前に書いていたら、純然たるミステリーとかサスペンスになっていたと思います。事実を基にした物語ってどういうことなんだろう、自分の小説が映像化、舞台化されたときの、あの居心地の悪さは何なんだろうとずっと考えていたので、このタイミングで書けてよかったと思います」
ここ数年で執筆は夜型から朝型に変わった。午前中に集中して書き、夕方、食料を買いに出たついでに散歩する。歩きながら考える。作中の小説家も、演奏会に行っても、友人とお酒を飲んでいても二人の女性のことが頭から離れない。
「実際、いつも頭のどこかで小説のことを考えています。これ使えるかなとか、ここにお話の種があるなとか。まあ職業病ですね」
この作品を書いていた6年の間に恩田さんは『蜜蜂と遠雷』で直木賞を受賞した。『灰の劇場』にはこうした自身の経験が描かれ、作家の日常に触れる楽しみもある。
「自分の記録にもなっています。小説を書く実況中継でもあり、それを書いている私の実況中継でもある。私にとっては記念になる小説になったかな。結果的に小説についての小説、フィクションについての小説になりました。小説には可能性がある、まだやりようがあるとすごく感じました」
小さな三面記事に強く引かれたのはなぜだったのか、その理由は書き終わった今もモヤモヤしたままだ。
「あの記事に呼ばれた、向こうがこっちを選んだとしか思えません」
実は最近になって二人の女性についての新たな事実が判明した。恩田さんは作品化を考えている。(仲宇佐ゆり)
※週刊朝日 2021年4月23日号







































