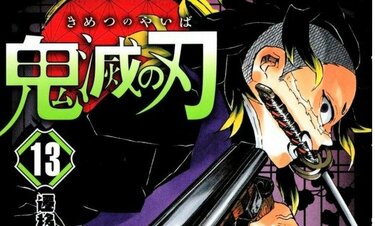年に一度、正倉院の宝物が特別に公開される正倉院展。今年は天皇の即位を記念し、東京でも正倉院宝物と法隆寺献納宝物を間近に感じられる正倉院の世界展が開催。悠久のときを超えた秘宝が一堂に会する。
文=鮎川哲也(本誌)
【関連記事】
年に一度公開される正倉院の秘宝 受け継がれてきた世界文化遺産
※週刊朝日 2019年10月4日号
年に一度、正倉院の宝物が特別に公開される正倉院展。今年は天皇の即位を記念し、東京でも正倉院宝物と法隆寺献納宝物を間近に感じられる正倉院の世界展が開催。悠久のときを超えた秘宝が一堂に会する。
文=鮎川哲也(本誌)
【関連記事】
年に一度公開される正倉院の秘宝 受け継がれてきた世界文化遺産
※週刊朝日 2019年10月4日号