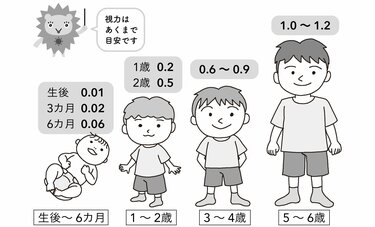丸一日、時間ができた。ふと、岩手県一ノ関のジャズ喫茶「ベイシー」に行こうと思い立った。
ちょうど、「ベイシー」の店主、菅原正二さんの著書『ぼくとジムランの酒とバラの日々』を読んでいたことも関係あるのかもしれない。この本を読みながら、「あれ、この本、前に読んでいるな?」と気づいた。調べてみると『ジャズ喫茶「ベイシー」の選択』という本のタイトルを変えての再出版本だった。『ジャズ喫茶~』の方は、ハードカバーで、『ぼくと~』の方は、ソフトカバー。読むには、ソフトカバーの方が持ちやすい。しばらくぶりに、もう一度、読むことにしたのだ。
数日前、友人が開催する日本酒の会に参加した。日本酒「司牡丹」を飲む会だったのだが、司牡丹酒造株式会社社長の竹村昭彦さん自らの説明を聞いたり、お酒を注いでもらったりして楽しんだのだが、そんなことに刺激されたのか、どこか、酒蔵に行ってみたいという思いが募っていたこともある。
そういえば、その少し前には、国際ソムリエ教会会長の田崎真也さんの主催する、「NO.1ソムリエが語る、新しい日本酒の味わい方」という本の出版記念と利き酒の会に参加して、田崎さんの話を聞きながら、日本酒の利き酒もした。
居酒屋探訪家?の太田治彦さんのテレビ番組を見たり、本を読んだりしているうちに、東京近郊以外の居酒屋にも行ってみたいという欲望が、わき上がっていたのも事実だ。そんなこんなで、三つも目的があるならいいだろうと自分を納得させて、新幹線の「はやて」に飛び乗った。
ちょうど昼時に一ノ関に着いたので、駅から、世嬉の一酒造株式会社が経営する「蔵元レストラン」に電話をする。こうやって思いつきで来たのはよいが、お休みだったりした経験が何度もあるからだ。電話をして、「これから伺いたいのですが、営業はしていますか?」とたずねると、なにか一瞬ためらって、「今、確認します」と言ってすぐに、「何人ですか?」と聞かれた。「一人です」と言うと、「それなら大丈夫です、いらしてください」ということなので、タクシーで行くことにした。でも、お店の方は、なにを気にしていたのだろう? 団体の対応は、むずかしいといったところだろうか?
タクシー乗り場に行くと、タクシーが何台も並んでいて、先頭の運転手は、運転席で眠っていた。待ちくたびれていたのだろう。窓ガラスを軽くたたいて、ドアを開けてもらい、乗り込んで目的地を言うと、「すぐそこだ」と言われる。さんざん待ったあげく、走行距離が短いので、不満を言ったのだ。この年齢になると、こんな嫌みにへこたれることもない。「わるいね」などと言いながら乗っていたが、外はあいにくの弱い雨、歩いて行きたい距離ではなかった。お店は蔵を改造したような建物で、きれいに整備されている。ここでは、ビールも造っているとのこと。
蔵ビールのお試し4種セットを注文する。
メインはお餅料理らしく、赤い塗り椀が九つ並んだ立派な料理が紹介されていたが、一人でたくさんの餅を食べる勇気もなく、豚肉の酒粕漬けと麹を使ったサラダを頼んだ。
ビールを飲み切らないうちに、日本酒も注文することにした。郷土地酒 飲み比べセットにした。一関地区の三つの蔵元のお酒を飲み比べできるものだ。
本醸造「世嬉の一」、本醸造「関山」、本醸造「磐乃井」の三種だ。
窓が開いていて、小雨が降っているが、わりと明るい庭の緑を見ながらの昼酒はよいものだ。
飲み終えてから、販売店やビールのタンクなどを見せてもらって、すぐ近くのジャズ喫茶「ベイシー」に向かった。
「ベイシー」は、営業していた。
「ベイシー」を訪ねるにあたって、このコラムの「音楽の聴ける店へ行こう」で取り上げたいなと思っていた。しかし、今までのお店は、前もって連絡をし、このコラムなどを前もって読んでいただき、時間の約束をし、取材をしていた。今回は突然の訪問で、突然、話を聞かせてほしいというのは、失礼ではないか、などと考えていたのだ。名乗らず訪問して、勝手に書いてしまったら、やはりまずいだろうか?などとも、考えならの訪問だった。もっとも、ここを訪れるのは3度目だし、菅原さんのお姿は、東京のイベントなどでもお見受けしている。しかし、お話をしたことはなかった。
どちらにしても、音楽を聴こうという気持ちで、お店の扉を押した。
お店の中には、クラシック音楽がかかっていた。曲名まではわからなかった。店主の菅原正二さんは、テーブルの上の原稿用紙に向かって執筆していた。
わたしが入っていくと、音楽はすぐにジャズに変わり、菅原さんが注文を取りに来た。ビールを注文した。
ビールをわたしのテーブルに置くと、菅原さんはついたてをはさんだ隣のテーブルのはす向かいに座り、「そのレンズはなに?」と話しかけてきた。
わたしは、カメラを持っていたのだ。わたしは「ツァイスの35ミリですけど、現行品です」と言った。カメラに興味を持っていない人には、なんのことかわからないかもしれないので、簡単に説明すると、ツァイスとは、ドイツのカメラ・メーカーの名前で、ライカと並んで、その優秀さが認められているブランドだ。わたしが持っていたカメラは、ソニーのα7Rというレンズ交換式の一眼レフで、ソニーは、そのツァイスと提携して、自社のカメラ用のレンズを作り販売しているのだ。
菅原さんは、そのレンズにすぐに気づいたのだ。
そして、すぐ席を立つと、自分のカメラを持ってやってきた。そして「このレンズ、いいよ」と言った。そのカメラは、わたしと同じ、ソニーのα7シリーズのカメラで、レンズは、ライカの50ミリだった。わたしもそのレンズは、持っていたので、「Rシリーズですね」と言った。Rシリーズというのは、ライカの一眼レフシリーズのことだ。ライカは、レンジファインダーが主流で、一眼レフは、それほど人気があるわけではなかったが、そのレンズの優秀さには定評がある。レンジファインファーとは、一眼レフがレンズを通過した画像を直接見ることができるシステムに対して、専用のファインダーを通して、写真の写る範囲を決めるスタイルのカメラだ。
菅原さんはほかにも、ツァイスやライカのレンズを見せてくれた。そして、カウント・ベイシーをはじめとする、彼の撮った写真を、どのレンズで撮影したかを話してくれた。実は、わたしも古いレンズにはまってしまい、何十本も買っている同類なのだ。
カメラやレンズというものは、今のデジタル・カメラで撮れば、おおむねきれいに撮影できる、しかし、レンズを変えていくと、同じ風景でも、そこに微妙に異なるニュアンスが生まれてくるものなのだ。特に、古い名レンズと言われるものは、その微妙な違い、それにこだわり撮影して、うまくいった場合に喜びを感じるものなのだ。
そこには、同じレコードをかけるのにも、オーディオの機器の違いや、セッティングで微妙に異なる違いに、こだわってきた菅原さんの人間性が見えたように思えた。
わたしは、菅原さんがわたしと同じたぐいのことに、こだわりを持っていることに気づき、自分が共感をもっていることに気づいた。
長くなってしまった。次回に続く。 [次回8/10(水)更新予定]
 小熊一実
小熊一実