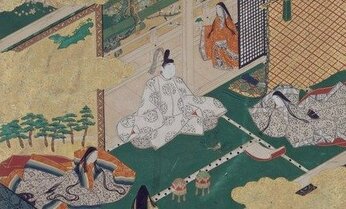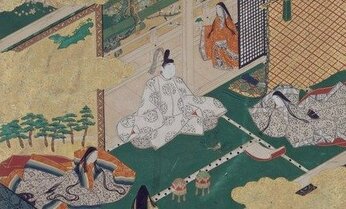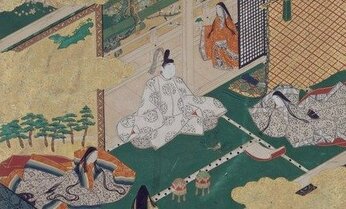関幸彦
プロフィール
●関幸彦(せき・ゆきひこ)
日本中世史の歴史学者。1952年生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士課程修了。学習院大学助手、文部省初等中等教育局教科書調査官、鶴見大学文学部教授を経て、2008年に日本大学文理学部史学科教授就任。23年3月に退任。近著に『その後の鎌倉 抗心の記憶』(山川出版社、2018年)、『敗者たちの中世争乱 年号から読み解く』(吉川弘文館、2020年)、『刀伊の入寇 平安時代、最大の対外危機』(中公新書、2021年)、『奥羽武士団』(吉川弘文館、2022年)などがある。
日本中世史の歴史学者。1952年生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士課程修了。学習院大学助手、文部省初等中等教育局教科書調査官、鶴見大学文学部教授を経て、2008年に日本大学文理学部史学科教授就任。23年3月に退任。近著に『その後の鎌倉 抗心の記憶』(山川出版社、2018年)、『敗者たちの中世争乱 年号から読み解く』(吉川弘文館、2020年)、『刀伊の入寇 平安時代、最大の対外危機』(中公新書、2021年)、『奥羽武士団』(吉川弘文館、2022年)などがある。
関幸彦の記事一覧