
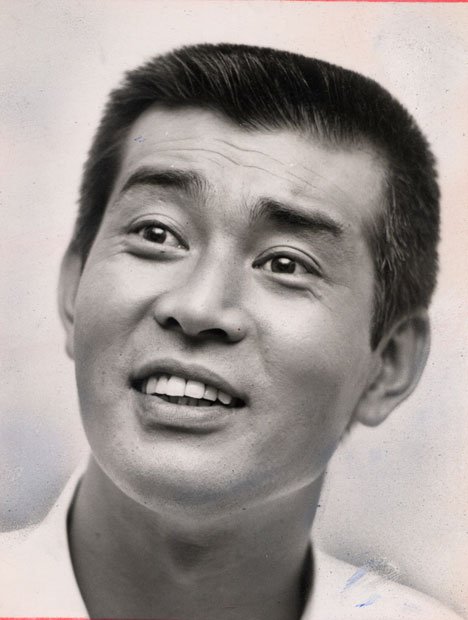
長谷川伸とともに“股旅もの小説”のパイオニアとして大衆文学史にその名が刻まれている子母澤寛。子母澤は「新選組始末記」で“新選組小説”の原型を作り、「勝海舟」で“幕末小説の開祖”になった大作家だが、近年では“座頭市”の生みの親として知られるのみの、“忘れられた作家”と言っていいのかもしれない。
「勝海舟」は、1941(昭和16)年10月から戦後の1946(昭和21)年12月までの6年間「日本経済新聞」他に連載された。敗戦を機にほとんどの連載小説が打ち切りになるなか、「勝海舟」はGHQに「江戸城明け渡しを分かりやすく説明したもの」として評価され、中断を免れて完結したという“幸運な時代劇小説”でもある。
1967(昭和42)年に最晩年の子母澤と対談した司馬遼太郎は「幕末よもやま」(『二十世紀末の闇と光―司馬遼太郎歴史歓談<2>』所載)のなかで、20歳くらいの時に「新選組始末記」を読んでどうしてもこれは超えられないと思い子母澤に会いに行って教えを請うた、と語っている。
子母澤が後進の司馬や池波正太郎に貴重な資料を惜しげもなく貸し与えたというエピソードはよく知られている。
1974(昭和49)年、12回目の大河ドラマはそんな子母澤寛の代表作の「勝海舟」を取り上げている。
勝海舟は幕末から維新にかけての動乱の時代、海軍塾や神戸海軍操練所の設立、第二次長州征伐の停戦交渉、江戸城無血開城など、溢れる才能を活かした幕臣の最重要人物。しかし坂本龍馬や西郷隆盛などから高い評価を受ける一方、徳川慶喜や同僚である幕臣からは嫌われてもいた毀誉褒貶の人でもある。
勝海舟には日活出身の渡哲也がキャスティングされ9話まで出演したが肋膜炎に倒れて降板、第10回以降は松方弘樹が引き継いだ。大河ドラマ始まって以来、異例の主役交代劇だ。
その勝の妻たみに扮したのが現在は陶芸家としても活躍している丘みつ子さんだった。丘さんは主役交代で騒然となった撮影現場での戸惑いを次のように語っている。
「渡さんとは日活時代に3本の映画で共演して大変よくしていただいていました。だから『勝海舟』での夫婦役を楽しくご一緒していたので、突然の降板は渡さんがあまりにお気の毒で口惜し涙を流しました。さあ本格的に始めようとしていた矢先でしたからね。第10話でいきなり松方さんの奥さんになって、まるで再婚したような錯覚に陥り戸惑いました。謹厳実直で初々しい渡さん、“遠山の金さん”のようにくだけた松方さん、まったくタイプが違うおふたりだったので平常心をとり戻すまで大変でしたね」
だが、「勝海舟」に降りかかったハプニングはそれだけではなかった。脚本を担当した倉本聰と演出陣が衝突したのだ。
倉本は一行たりとも了解なしで台詞を変えることは許さず、脚本読みと立ち稽古まで立ち合って作家の意図を俳優に伝えようとするタイプ。一方、演出家やプロデューサーは作品全体のアンサンブルや制作を統括する責任を負っているので、倉本の方法論をすべて受け入れることは出来ない。両者の溝は深まるばかりだったが、紆余曲折の末に倉本が降板するという形で決着する。怒りが収まらなかった倉本はなぜか札幌に逃避し、そのまま定住してしまう。余談だがこの降板劇がなければ名作「北の国から」も「昨日、悲別で」も生まれていなかった。
そのときの模様を丘さんは次のように語っている。
「撮影現場は騒然とした雰囲気でした。いろいろな情報が飛び交って、スタッフも俳優もみんな地に足が着いていないような感じと言ったらいいのでしょうか。何が本当で、誰の言っていることを信じていいのか分からないので、なるべく耳を塞いでいましたね。自分が無くなっていくような感じと臨戦態勢とでも言ったらいいような感じがないまぜになったような気持ちになったのを覚えています。そのときの衝撃は今でも昨日のことのように覚えています」
主役交代も大事件だが、脚本家降板も大河始まって以来の大ハプニングだった。ふたつのアクシデントを体験した丘さん。
「俳優にとって一年間という長丁場を乗り越えるのは本当に大変なことですが、それを乗り越えれば自分を成長させることが出来る、一段上に登ることが出来ると自身に言い聞かせて過ごした一年でした。渡さんと倉本さんの降板という大事件を体験しましたが、43年前の出来事がそれからの自分の成長に繋がっていると思っています」
主役以外でも萩原健一の人斬り以蔵、藤岡弘、の坂本龍馬などが印象に残った「勝海舟」。全52話のうちNHKには14話分しかビデオテープが保存されていないが(昨年、藤岡弘、が個人的に録画した11話分をNHKアーカイブスに提供)、テレビドラマ史上、この上なく貴重な映像だ。(植草信和)





































