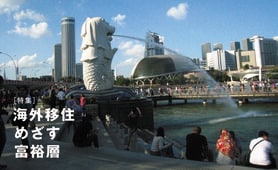だが、1度のフライトで1千万円かかるなどコスト面での課題がある。しかも、台風と違い、いつどこで発生するか予測が困難なため、観測ポイントを定めにくい。まずは、来年にも、前線や台風の東側といった線状降水帯ができやすい条件を狙った観測を試みたいと語る。
「将来的には、12時間前に線状降水帯の発生を予測できるようにしたいと考えています」(同)
一方、陸からのアプローチを試みるのは、福岡大学の白石浩一助教(地球物理学)らだ。気象庁気象研究所(茨城県つくば市)と共同で、「水蒸気ライダー」と呼ばれるレーザー光を利用する最新式の観測機器を使い、水蒸気を観測する。レーザー光を上空に向けて発射し、大気中の水蒸気に当たって散乱した光を観測することで、水蒸気量を推し量る。
■水蒸気量計測に成功
現在、水蒸気ライダーは、長崎市と鹿児島県の離島・下甑島の2カ所に設置。昨年、長崎に設置した水蒸気ライダーで、実際に発生した線状降水帯に流入する空気に含まれる水蒸気の計測に成功した。
白石助教は言う。
「水蒸気を計測してそのデータを利用することで、線状降水帯の発生予測精度を上げることができれば、激甚化する豪雨被害の軽減に貢献できるはずです。少しでも減災に貢献できるよう、予測に役立てられるようにしたいと思っています」
梅雨が明けても、秋まで線状降水帯は発生する。気象庁によると19年は8月に5回、9月に3回、10月にも5回、線状降水帯に関する情報を出している。先の片山さんは言う。
「今では『これまで経験したことのない大雨』は、通用しなくなっています。いつどこで降ってもおかしくありません。雨の降り方がいつもと違うという感覚を持った時は、早めの避難行動をとることが大切です」
(編集部・野村昌二)
※AERA 2021年7月26日号