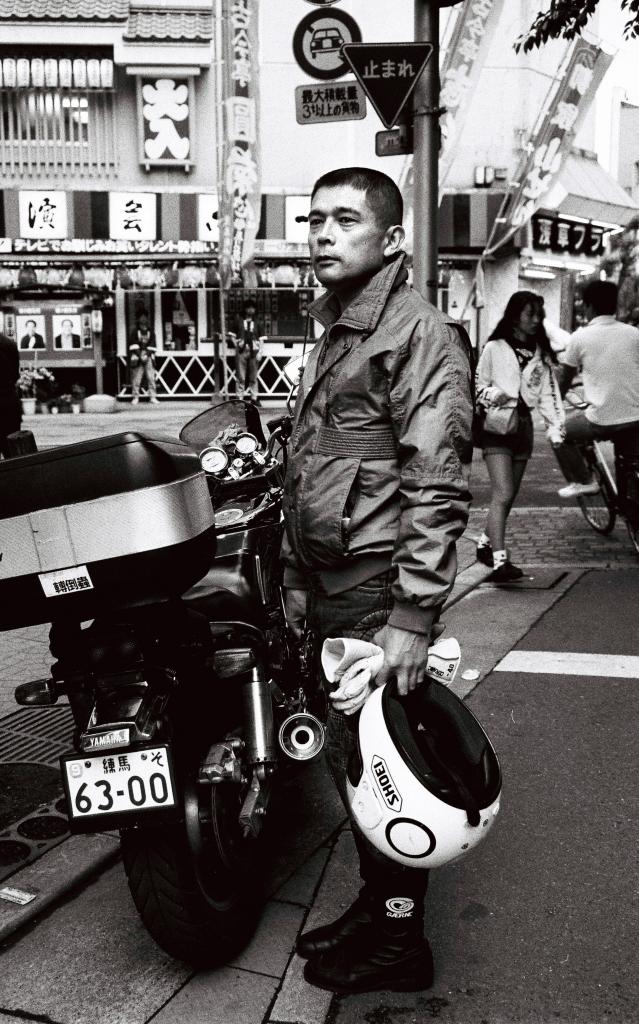
自分は完璧じゃないと思い込んできたから、噺家になっても、つねに完璧を求めて、自分に厳しく、精進した。
戦争中は、家族の中で彼だけが父親の故郷である宮城県の岩沼に疎開させられた。親にしてみれば大事な長男を戦火から守りたい一心だったのだろうが、ひとりだけ遠くにやられたことで、またもいじけた。
けれども、その地で、おばさんに温かく迎え入れられて、存分に甘えさせてもらい、心にうるおいを取り戻す。
こんな親への複雑な思いや子どもの気持ちが、「子別れ」や「藪入り」はもとより、「寝床」「茶の湯」に登場する小僧のささいなせりふにも投影されている。また、このときの体験で、「馬の田楽」「蒟蒻(こんにゃく)問答」など田舎を舞台にした話や、「宗論」の権助、「百川」の百兵衛の情景・人物描写が無理なくできた、と感謝していた。
父親は、剛蔵少年にも教育者の道を歩んでほしいと願った。しかし、剛蔵少年は中学時代には落語に夢中になってしまい、都立青山高校に天才少年あり、といわれるほどになる。ラジオ東京(現TBSラジオ)の「しろうと寄席」に出演し、15週勝ち抜いたのだ。
高校生というだけで珍しがられて注目を浴びただけのこと、と本人は極めて冷静だったが、評判になる。
「30分の番組で、噺なんかほとんどしてねえ、うまいも下手もねえ、おかしいじゃねえか、と思ったけど、スターに祭り上げられてしまった」
おかげで、教師になる道を、両親もあきらめてくれ、五代目小さんに弟子入りがかなった。
◆志ん朝と談志 二人のライバル
噺家になろうと決める前、小さん師匠と「しろうと寄席」の狭い楽屋でふたりきりになったことがあった。小さん師匠は、何もいわないで、ただじっと正面を見据えていた。
「そのときの小さんという人の目が、澄んでいて、とってもきれいだった。その目に惹かれた。惚れたんですよ。その後、師匠の『千早振る』を聴いて、度肝を抜かれた。面白いのなんのって」
まるで男と女の恋愛感情のような、一目惚れだったという。





































