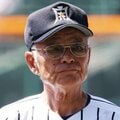また、同社では2012年に、キンミヤ自体を凍らせてシャーベット状にし、ホッピーなどで割って楽しむパウチ入りの「シャリキン」を開発し人気商品になった。きっかけは、都内のある得意先がキンミヤを凍らせるメニューを独自に出していることを知ったこと。それをヒントに商品化に至ったという異例の形だ。
「顔の見えるお付き合いをする中で、こうしたいい商品を生み出すことができたと実感しています」(伊藤さん)
人がまさに財産なのである。
■「キンミヤ・ブルー」のインパクト
ならば、キンミヤの象徴である、あのきれいなブルーのラベルは誰がデザインしたのか。愛好家には「キンミヤ・ブルー」と持ち上げる人がいるとかいないとか。4リットルサイズの生産を減らし、見慣れない瓶が店内に並んだ時、あのラベルにインパクトを感じた人もいるだろう。
「実は、誰がどんな経緯でデザインしたのか、記録がなくわからないんです。生産当初から、おそらくあのデザインだったのだろうとは思いますが。印刷会社に元の版があるので、ずっと使い続けています」
永遠に解けぬであろう謎。答えはさておき、キンミヤは今宵も、呑兵衛が集う酒場で「名脇役」のお務めを果たす。
(AERAdot.編集部・國府田英之)
こちらの記事もおすすめ 【前編】下町の名脇役「キンミヤ焼酎」が右肩上がりの売れ行き 小瓶に変えたら人気上昇の意外な理由