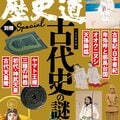何よりも秀吉の本隊は、備中・高松城の戦いから「中国大返し」まで働き通しで疲れ切っているはずであり、縦横無尽に戦場を駆け回ることもできないだろう、という予測もあった。光秀はそこに勝機を見出し、その勝機に賭けた。
結果としての惨敗だったが、この合戦での戦死者が、明智方3千余人、秀吉方3千300余人とされているように敗者と勝者の戦死者の数が拮抗していることは、少なくとも合戦前半は明智方が優勢だったことを示すという(旧参謀本部『日本戦史・山崎の役』)。
勝龍寺城を脱出した光秀主従一行は、伏見から醍醐を抜けて近江方面に向かった。深夜になっていた。
「天下人」の意識があった光秀
再挙の可能性はあり得たか?
光秀には、先ず坂本城に無事に辿り着くことが最優先であった。本拠地・坂本城で再起を期し、安土城にいる明智秀満の軍勢1万を軸にして、秀吉軍と対峙する。この間に、直前まで秀吉と戦っていた毛利輝元や、上杉景勝、長宗我部元親などとの連携を図り、さらには備後・鞆にいる将軍・足利義昭を奉じて全国の武将に足利幕府の再興を呼び掛ける。これが光秀再起の主軸ではなかったか。
光秀は7日の時点で朝廷からの使者・吉田兼見から誠仁親王の「京都を守護するように」との言葉を受けていた。つまり光秀は、謀反ではなく京都の守護者として朝廷にも認知された、という自負があった。いわゆる「天下人」としての意識である。
もし、坂本城までが秀吉軍に落とされるような憂き目に遭うとしたら、その場合は琵琶湖の水運を使って塩津まで渡り、そこから敦賀を目指し、さらに海路(日本海)で毛利領か上杉領に向かえるではないか。光秀の脳裏には、建武親政の第一功臣とされながらその政権に背いて北畠顕家らとの合戦に敗れて九州に落ち延びたものの、再挙して湊川で楠木正成らを敗って征夷大将軍に任じられた足利尊氏の故事が去来していた。分国(地方)に落ち延びることで再挙は可能、という「足利尊氏の成功」が光秀の脳裏にはあったのだ。
だが、現実は厳しかった。この時点で光秀は知らなかったが、坂本城は十四日未明には山岡景隆・堀秀政など秀吉に味方する軍勢に囲まれていた。光秀が最も信頼していた明智秀満は、安土城から軍勢を率いて坂本城に入ったが、十五日には落城する。秀満は、坂本城にあった茶器・墨跡・刀など「天下の名物」とされる品々を目録を付けて堀秀政に送った。「私物化してはならないし、失っては惜しい」という配慮からであった。この後、秀満は自分の家族を含む明智一族もろとも刺殺し自害して果てた。
また山崎合戦後に、光秀らと離れ離れになり近江の堅田に潜伏していた光秀の家老ともいえる斎藤利三は、捕縛されて京都市中を引き回されて刑死する。
こうした事実は、光秀が何とか坂本城に戻れたとしても光秀の再起は不可能であることを示すものである。光秀が落ち武者狩りで殺されず生き延びていたとしても、恐らく坂本城落城の時点で光秀は主従共々自刃して果てたであろう。
こちらの記事もおすすめ 戦国最大のミステリー「本能寺の変」 明智光秀をそそのかした”黒幕”は誰だ?