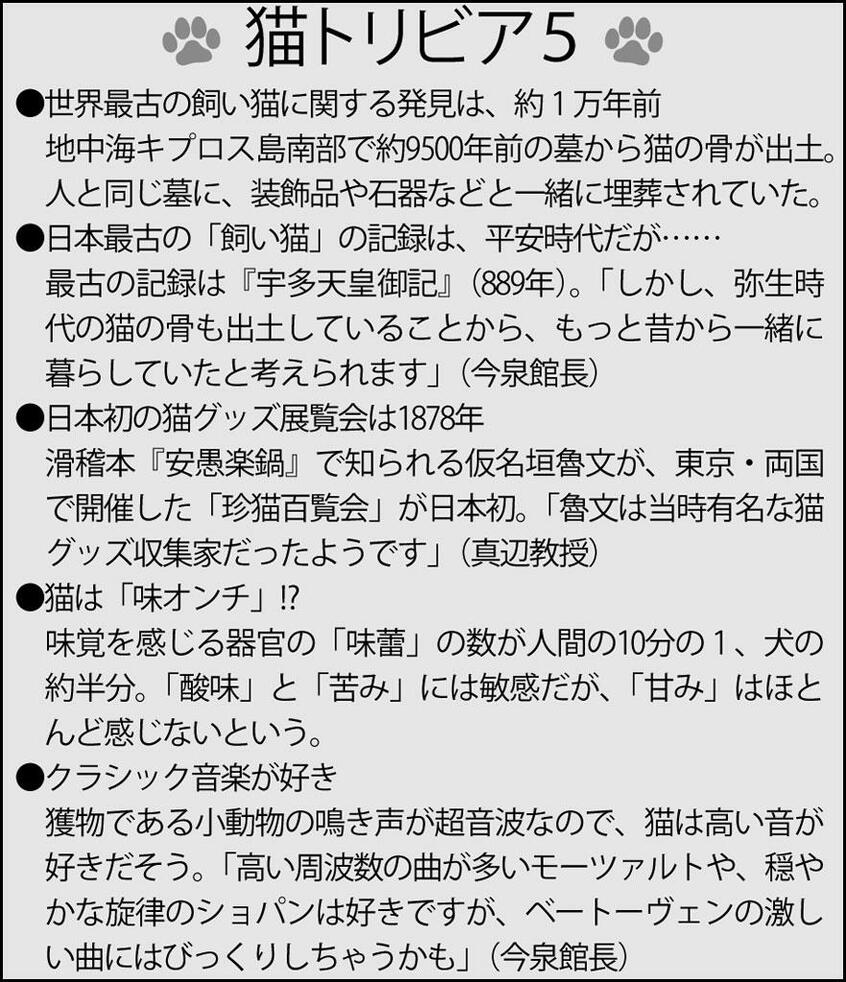
単に猫の「本能」がさせている行動だったとすると、ショックだが……。
「夢を壊すようなことを言ってしまいましたが、がっかりするのはまだ早い。じつは飼い猫特有の、飼い主への感情があるんですよ」(同)
猫の脳は、論理的思考をつかさどり別名「霊長類の脳」と呼ばれる大脳新皮質が少なく、その行動には本能的な感情である「情動」が強くかかわっている。興味がある、怖い、子猫などの世話をしたい、食べたい、眠いなどだ。人の感情は「喜怒哀楽」と言われるが、猫には「喜怒楽」の感情はあるものの、厳しい野生では、悲しんでいたら生きていけないため、「哀」に当たる悲しみの感情があまりないという。
しかし、飼い猫に限っては、野生ではあまり見られない、安心しきってリラックスした状態、つまり飼い主への「愛」を見せる猫が多いという。耳は外側に向き、ヒゲはだらんとたれ、全身は脱力して、くねくねと転がる。「喜怒“愛”楽」が、飼い猫の感情なんだとか。そう、猫はあなたを愛しているのだ。
とはいえ、おなかを見せているからとなでてあげると3秒ほどは喜ぶが、その後ハッとわれに返り、弱点をさらしていることに気が付いて攻撃してくることも。実に気まぐれだが、そんなところもまた魅力の一つなのかも。
「愛」を持っていることを示す一つの事例が、飼い猫の「イクメン化」だという。そもそもライオン以外のネコ科動物は、父となったオスがメスや子どもに近づかず、むしろオスによる子殺しのリスクさえあるというのが定説だった。しかし、今泉館長によると、昨今は頻繁に子どもの様子を見に来たり、においをかいだり、じゃれて遊んであげたりするオスの姿が報告されているという。
「オス猫が子育てをするという、ある種人間的な側面が見られたことは、新鮮な驚きでした。猫と人間の絆は、今後ますます深まっていくでしょう」(同)
今や、人間にとってなくてはならないパートナーとなった猫。しかし、歴史をひもとくと、猫はずっとかわいがられてきたわけではない。江戸時代には「化ける」「たたる」などとして忌み嫌われ、その後も人気で犬に水をあけられてきた。




































