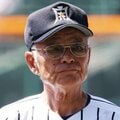起業家というのは身の回りの不便や社会の課題に気づいて、変えようと行動する人です。多くの人は気づいていても何もしない。起業家たちはテクノロジーやスキルを使って問題を解決します。例えばウーバーの創業者、トラビス・カラニックはサンフランシスコの駐車場で、ドライバーが乗ったまま止まっているリムジンを見て「デートの時に借りられないか」と思いついた。それでスマホの位置情報機能を使ってライドシェアのサービスを立ち上げたら、6年で株式時価総額が10兆円を超えてしまった(現在は7兆8千億円)。同じシェアビジネスを民泊でやったのがAirbnb、印刷所でやったのが日本のラクスル、家電や洋服など個人の所有物でやったのがメルカリです。
共通しているのは「こんなにものが溢(あふ)れているのに使われていない」という社会課題の解決です。モノをたくさん作ってたくさん売りたい人たちには都合が悪い話かもしれませんが、「本当にそのやり方でビジネスを20年、30年続けられますか」と問えば自(おの)ずと答えは見えてくる。そういう意味では日本でも米国と同じことで起業のムーブメントが起きているわけですが、残念ながらスケールが違う。
──日本は起業の新陳代謝が遅く、ユニコーン(評価額10億ドル以上の未上場企業)が生まれません。
伊佐山:本にも社会課題を見つけて解決しようとしている人たちはいます。しかしスタートアップを立ち上げても、なかなかスケールしない。お金がないからなのか、技術がないからなのか。実は両方ともあるんです。日本でお金と技術を持っているのは大企業です。「日本の大企業が本気になったら負けるはずがない」というのが、米国のVCで働いた僕の結論でした。(敬称略)(文/ジャーナリスト・大西康之)
※AERA 2022年4月4日号より抜粋